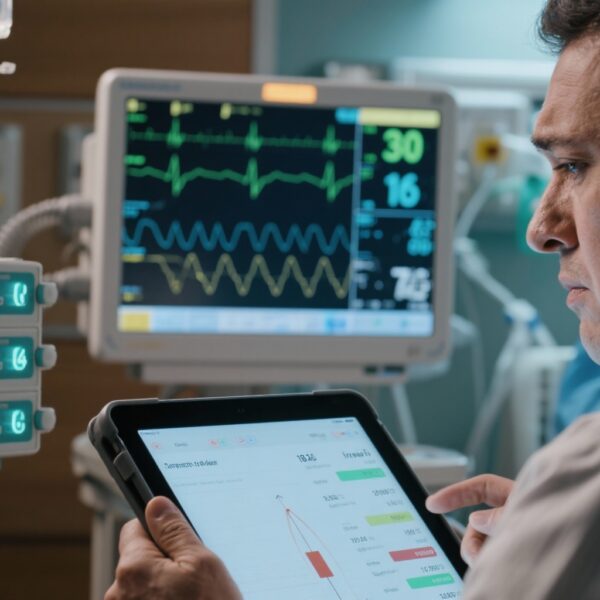ハイライト
– 単施設、二重盲検RCT(n=130)において、難治性敗血症ショック患者における補助的なテリプレッシンが、6時間後にMAP≧65mmHgを達成し、総カテコールアミン相当量<0.2mcg/kg/minの患者の割合を増加させた(22.7% vs 9.4%; P=0.039)。
– 28日間の死亡率には統計的に有意な差はなかった(60.6% テリプレッシン vs 64.1% プラセボ; P=0.68)。
– 手指虚血の頻度は両群で類似しており、比較的高かった(約28%)、強力な血管収縮薬の安全性に懸念が残る。
背景
敗血症ショックは集中治療室での主な死因の一つであり、現在のガイドラインに基づく第1選択の血管収縮薬はノルエピネフリンである。難治性ショックでカテコールアミン支持が必要となる患者に対して、カテコールアミン以外の血管収縮薬(例えば、バソプレシンやそのアナログ)を追加することで、動脈圧を回復し、カテコールアミン曝露を減らし、カテコールアミン関連の悪影響を制限するという戦略が一般的である。
テリプレッシンは、V1受容体活性が強く、半減期が天然のバソプレシンよりも長い合成バソプレシンアナログである。動脈細動脈収縮を引き起こし、平均動脈圧(MAP)を上昇させ、カテコールアミンの必要性を低減する。しかし、地域虚血(手指、腸間膜、心筋)の懸念と、患者中心のアウトカム(死亡率など)への影響が明確でないという問題が残っている。
研究デザイン
研究者は単施設、前向き、二重盲検、無作為化、プラセボ対照試験を集中治療室で実施した。高用量カテコールアミン(ノルエピネフリン>0.2mcg/kg/minまたはエピネフリンを使用)が必要な成人敗血症ショック患者を1:1で補助的なテリプレッシンまたはプラセボに無作為に割り付けた。試験には130人の患者(テリプレッシン群66人、プラセボ群64人)が登録された。基線特性と重症度はバランスが取れており、各群の基線ノルエピネフリン相当量の中央値は0.39mcg/kg/minであった。
事前に規定された主要評価項目は、無作為化後6時間以内に平均動脈圧≧65mmHgを達成し、総カテコールアミン相当量が0.2mcg/kg/min未満の患者の割合であった。
主要な知見と解釈
主要評価項目。 6時間時点でテリプレッシン群で主要評価項目を達成した患者の割合が多かった:22.7% 対 9.4% プラセボ群(報告された相対リスク[RR]=1.53, 95% CI 1.09-2.14; P=0.039)。これは約13.3ポイントの絶対差を示し、この血液力学/カテコールアミン終点を達成するために必要な治療数(NNT)は約8である。
臨床解釈:補助的なテリプレッシンは、MAPで定義される早期血液力学安定化の確率を高め、カテコールアミン曝露を減らした。カテコールアミン量の減少は概念的には魅力的であるが、高カテコールアミン曝露は不整脈、代謝障害、免疫調整などの悪影響に関連している。しかし、短期的な減少が患者中心のアウトカムの改善につながるかどうかは不確かなままである。
死亡率と患者中心のアウトカム。 28日間の死亡率は両群で高く、統計的に有意な違いはなかった:60.6%(テリプレッシン)対 64.1%(プラセボ)(RR=0.93, 95% CI=0.66-1.31; P=0.68)。この試験からテリプレッシンが死亡率を低下させたという証拠はなかった。
臨床解釈:短期的な血液力学サロゲートに対する有利な効果にもかかわらず、テリプレッシンはこの集団の28日間生存率を変えていない。試験は比較的小規模で、死亡率に対して十分な検出力がなかった可能性がある。全体として死亡率は高かった。早期のカテコールアミン必要量の減少が生存率、臓器支持期間、機能的アウトカムの改善につながるかどうかはまだ証明されていない。
安全性のシグナル。 テリプレッシン群の28.8%とプラセボ群の27.4%で手指虚血が発生した(P=0.86)。これらの頻度は注目に値し、多くの血管収縮薬で報告されるものよりも高いが、試験集団は重症ショックで基線時に高用量の血管収縮薬曝露があった。
臨床解釈:テリプレッシンは強力な血管収縮薬であり、地域虚血に関する正当な懸念を引き起こす。この試験では、手指虚血の頻度は両群で類似していた—難治性ショックにおける高背景率を反映している可能性がある—が、V1アゴニストを使用する際の虚血合併症に対する注意は不可欠である。詳細なデータ(腸間膜虚血、手術が必要な四肢壊疽、心筋虚血など)は要約には含まれていなかったが、全文報告で確認するべきである。
統計と報告の注意点。 要約では、主要評価項目のRR=1.53、95% CI 1.09-2.14と報告されているが、原始的な割合(22.7% 対 9.4%)から計算される未調整比率は約2.4に近い。この不一致は、基線共変量に対する調整分析、報告の慣例、または抄録内の転記ミスを反映している可能性がある。読者は、報告されたRRを導出した解析方法を確認するために全文を参照すべきである。
先行研究との文脈
以前の大規模試験では、敗血症ショックにおける補助的な血管収縮薬としてのバソプレシン(天然ホルモン)が評価されていた。VASST試験(Russell et al., NEJM 2008)では、バソプレシンをノルエピネフリンに追加しても全体的な死亡率の改善は見られなかったが、ショックの重症度が低いサブグループでは利益が得られた。SOAP II(De Backer et al., NEJM 2010)は、ノルエピネフリンとドーパミンを比較し、ノルエピネフリンが不整脈が少なく、結果が良好であることを示した。Surviving Sepsis Campaignガイドラインは、ノルエピネフリンを第1選択とし、MAPを上げたり、ノルエピネフリンの必要量を減らしたりするためにバソプレシン(固定用量)を補助的に使用することを推奨するが、死亡率の改善に対する強力な証拠は提供していない。
テリプレッシンは、バソプレシンとは薬理学的に異なる(持続作用のあるV1アゴニスト)であり、小規模な生理学的研究ではMAPを上昇させ、カテコールアミンの必要性を減らすという有望な結果を示している。しかし、臨床アウトカムを検討するための強力な多施設試験は、最近のデータ(現在の試験など)が出るまで不足していた。
専門家のコメントと制限事項
この試験の強みには、無作為化、二重盲検、明確に定義された難治性ショックを持つ重症患者の登録が含まれる。主要評価項目は、血液力学的およびカテコールアミン節約の終点として客観的かつ臨床的に関連性が高い。
重要な制限事項には、単施設での実施、比較的小規模なサンプルサイズ、早期の生理学的サロゲートを主要評価項目として選択したこと(死亡率、通気フリー日数、腎代替療法フリー日数、機能状態などの患者中心のアウトカムではなく)が含まれる。試験の高基線血管収縮薬用量と高死亡率は、他の設定でのショックの重症度が異なる場合の一般化可能性を制限する可能性がある。両群での予想外に高い手指虚血の頻度は、慎重な審査と追加の報告詳細(重症度、介入の必要性、可逆性)を必要とする。
未解決の問題には、テリプレッシンの最適投与戦略(ボルス対持続点滴、固定用量対体重ベース)、最も利益を得られる患者の特定方法(バイオマーカー、血液力学的フェノタイプ、カテコールアミン依存性)、虚血合併症の安全性トレードオフが含まれる。メカニズム的には、テリプレッシンの血管収縮作用は中心循環圧を維持しながら、地域循環圧を悪化させる可能性がある。モニタリング戦略と投与量調整アルゴリズムの開発が必要である。
臨床的意義
難治性敗血症ショックを管理する医師にとって、この試験はテリプレッシンが早期の血液力学目標を達成し、カテコールアミン曝露を減らすことができる可能性を示唆している。しかし、死亡率の改善は示されず、虚血リスクが懸念されることから、テリプレッシンは慎重に選択された患者に対する救済的な補助療法と考えるべきであり、ルーチン療法ではない。使用する際には、虚血合併症を監視し、末梢循環を頻繁に再評価し、MAP目標が達成された場合には急速な投与量の段階的削減を検討すべきである。
結論
この無作為化、プラセボ対照試験は、難治性敗血症ショック患者において、補助的なテリプレッシンが6時間後にMAP≧65mmHgを達成し、カテコールアミン用量を低下させる可能性があることを示しているが、28日間の死亡率の改善は見られなかった。両群での手指虚血の頻度は類似しており、安全性に懸念があり、詳細な有害事象報告が必要である。より大規模な多施設試験が、患者中心のアウトカム、最適な投与量、患者選択、安全性モニタリングを明確にするまで、難治性敗血症ショックに対して広範囲に推奨される前にテリプレッシンの使用は慎重に行われるべきである。
資金提供とClinicalTrials.gov
試験登録:ClinicalTrials.gov NCT04339868(2020年4月7日登録)。資金詳細は、ここに提供された要約には含まれていない。読者は、資金源、利害関係の開示、プロトコルの詳細については、全文の出版記事を参照するべきである。
参考文献
1. Tongyoo S, Chayakul C, Aritajati T, Tanyalakmara T. Adjunctive terlipressin versus placebo in the treatment of refractory septic shock: a randomized, placebo-controlled trial. Crit Care. 2025 Oct 21;29(1):443. doi: 10.1186/s13054-025-05669-0. PMID: 41121365; PMCID: PMC12538821.
2. Russell JA, Walley KR, Singer J, et al.; VASST Investigators. Vasopressin versus norepinephrine infusion in patients with septic shock. N Engl J Med. 2008 Aug 14;359(9):877-887. doi:10.1056/NEJMoa071434.
3. De Backer D, Biston P, Devriendt J, et al.; SOAP II Investigators. Comparison of dopamine and norepinephrine in the treatment of shock. N Engl J Med. 2010 Sep 30;362(9):779-789. doi:10.1056/NEJMoa0907118.
4. Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al.; Surviving Sepsis Campaign Guidelines Committee including the Pediatric Subgroup. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. Intensive Care Med. 2021 Nov;47(11):1181-1247. doi:10.1007/s00134-021-06506-y.