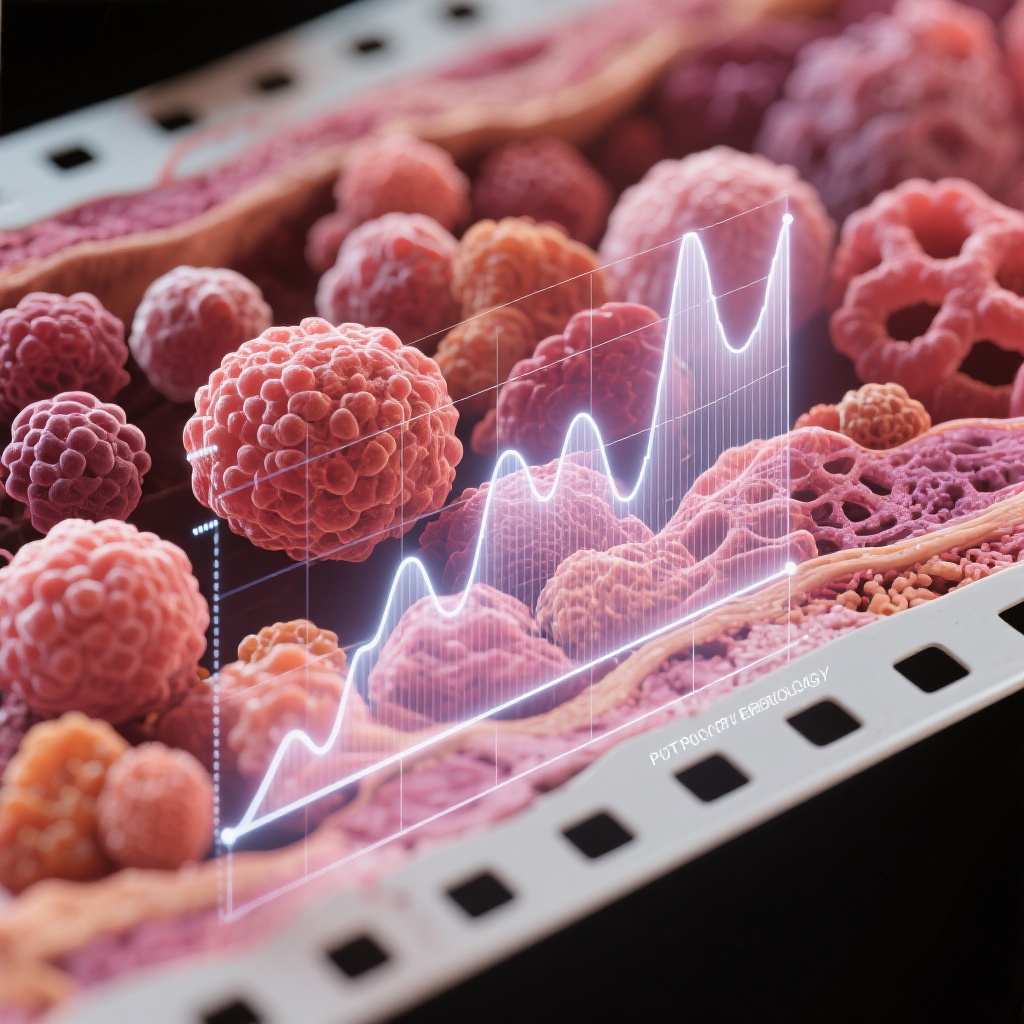ハイライト
- 日本での66年間にわたる148万件の解剖データの分析によると、55.2%の症例でがんの診断が含まれていました。
- 多発原発がんの有病率は約8倍に増加し、1974年の1.8%から2023年の14.4%となりました。
- 生存中に診断されなかった潜在性がんは、1986年の1.7%から2023年の7.4%に増加しました。
- これらの潜在性がんの約7.3%は、解剖時にすでに転移を示していました。
序論:悪性腫瘍の沈没した氷山の地図化
通常のがん統計は、主に臨床診断と死亡証明書から導き出されるものであり、疫学的な氷山の先端を表しているだけです。何十年にもわたり、医師や研究者たちは、臨床で観察されるがんの発生率と人口内の悪性腫瘍の真の有病率との乖離を認識してきました。この「隠れた負担」には、患者の一生を通じて無症状で診断されず、死後検査で初めて発見される潜在性がんが含まれます。
これらの未診断の悪性腫瘍のトレンドを理解することは、現在のスクリーニングプログラムの効果、診断技術の正確さ、過剰診断の可能性を評価する上で重要です。JAMA Network Openに掲載された画期的なコホート研究は、世界で最も急速に高齢化している社会の一つである日本の66年間の解剖データを提供し、がんの負担がどのように変化してきたかを長期的に示しています。
研究デザイン:66年間の病理記録
この包括的なコホート研究では、日本病理学会が維持する全国レジストリである「日本病理解剖症例年報(APAC-J)」のデータを使用しました。研究者は、1958年から2023年にかけて記録された1,486,557件の病院ベースの解剖データを分析しました。研究対象者の平均年齢は59.1歳で、男性が62.5%を占めていました。
主要な目的は、総合的ながん、多発原発がん、潜在性がんの長期的なトレンドを評価することでした。潜在性がんは、患者の生涯中で臨床的に疑われたり診断されなかったが、解剖時に病理学者によって特定された悪性腫瘍を指します。研究者はまた、「解剖における濃縮比」という新しい指標を導入し、特定のがんの解剖レジストリにおける有病率を全国的な死亡統計と比較することで、未診断疾患のリスクが高い集団を特定しました。
多発原発がんの進化
この研究の最も目覚ましい発見の一つは、多発原発がんの劇的な増加です。1974年には、がんを伴う解剖症例の1.8%のみが複数の原発腫瘍を伴っていましたが、2023年にはこの割合が14.4%に上昇しました。この傾向は、長寿化による独立した発がんイベントの時間の増加や、異なる原発部位と転移の区別を可能にする改善された病理技術など、いくつかの要因を反映していると考えられます。
現代のがん専門医にとって、多発原発がんの増加は治療パラダイムを複雑化させています。再発や転移と誤認される可能性のある第二の悪性腫瘍を見逃さないためには、より厳密な診断が必要となります。治療の意味は、手術アプローチから全身療法の選択まで、大きく異なります。
潜在性がん:隠された負担の明かされる
1986年以降、レジストリは系統的に潜在性がんを追跡してきました。この期間に実施された811,159件の解剖のうち、34,174人の36,133件の潜在性がんが同定されました(4.2%)。しかし、検出率は一定ではなく、1986年の1.7%から2023年の7.4%に増加しました。
この潜在性がんの検出率の増加は、人口に存在する未診断疾患の貯水池が増大していることを示唆しています。この増加の一部は、より詳細な解剖手続きによるものかもしれませんが、生物学的な現実も指摘しています:高齢化に伴い、進行が遅い悪性腫瘍の有病率が増加します。研究によると、「濃縮比」は特に、思春期/若年成人(15〜24歳)と高齢者(80歳以上)の2つのグループで高まっています。若い世代では、早期に検出されにくいが激しい悪性腫瘍が原因である可能性があります。高齢者では、慢性で年齢に関連した腫瘍の蓄積が原因である可能性があります。
前立腺および甲状腺組織での不均衡な結果
臨床発生率と解剖有病率の乖離は、前立腺がんと甲状腺がんで最も顕著でした。75〜79歳の男性では、潜在性前立腺がんは4.5%の解剖症例で同定されました。2017〜2021年の臨床発生率データと比較すると、解剖有病率は6.9倍高かったです。
甲状腺がんの結果はさらに劇的でした。50〜54歳のグループでは、男性の0.9%と女性の1.7%で潜在性甲状腺がんが見つかりました。これらの数値は、それぞれ臨床発生率の94.5倍と60.7倍高かったです。これらの結果は、特に甲状腺や前立腺組織において、多くの検出された腫瘍が患者が長生きすれば臨床症状や死亡を引き起こさなかった可能性があるという過剰診断の現象に対する強力な病理学的証拠を提供しています。
潜在性腫瘍の転移の可能性
潜在性がんの研究における重要な問いは、これらの「隠された」腫瘍が本当に進行が遅いか、それとも生命を救う機会を逃したのかです。研究者は、36,133件の潜在性がんのうち7.3%(2,649件)が解剖時点で既に転移していたことを発見しました。この結果は、診断されなかったがんの一部が有意な生物学的な攻撃性を有していたことを示すものであり、深刻な問題を提起しています。
潜在性症例における転移の存在は、非侵襲性腫瘍の過剰診断への懸念とは別に、転移能力を持つ攻撃的な腫瘍の「未診断」ががん死亡に寄与している重要な臨床的課題であることを示しています。
専門家のコメント:過剰診断のジレンマを乗り越える
日本の解剖データは、現代医学に二重の課題を提示しています。一方、甲状腺や前立腺がんの臨床と病理の有病率の大きな乖離は、特定の低リスク集団でのスクリーニングの保守的なアプローチを支持し、過剰治療の害を避けることが求められます。他方、転移の可能性のある潜在性がんの増加は、現在の診断網がまだ致死的な悪性腫瘍を見逃していることを示しています。
研究の「濃縮比」は、このジレンマを洗練された視点で捉えています。特定の年齢層(15〜24歳のグループなど)で解剖有病率が臨床死亡率を大幅に上回る場合、診断革新が最も緊急に必要な領域を特定することができます。さらに、多発原発がんの増加傾向は、一がんの生存者が再発だけでなく、全く新しい悪性腫瘍の監視を必要とする生涯の監視を必要とする可能性があることを示しています。
結論
この148万件以上の解剖データに基づく66年間の分析は、日本のがんの変動する風景を明確にしています。未診断がんの重要なかつ増加する貯水池、多発原発悪性腫瘍の顕著な増加、そして臨床検出を逃れる持続的な転移性疾患の現実を強調しています。これらの結果は、解剖が疫学的真実の「ゴールドスタンダード」としての持続的な価値を強調しています。臨床界にとっては、致死性のがんを検出しつつ非侵襲性のがんを見過ごすことなく、スクリーニング戦略を精緻化するための呼びかけとなっています。
参考文献
- Uozaki H, Kikuchi Y, Watanabe M, et al. Trends in the Hidden Burden of Cancer in an Autopsy-Based Study Over 66 Years in Japan. JAMA Netw Open. 2026;9(2):e2557812.
- Welch HG, Black WC. Overdiagnosis in cancer. J Natl Cancer Inst. 2010;102(9):605-613.
- 日本病理学会. 日本病理解剖症例年報. 東京, 日本.