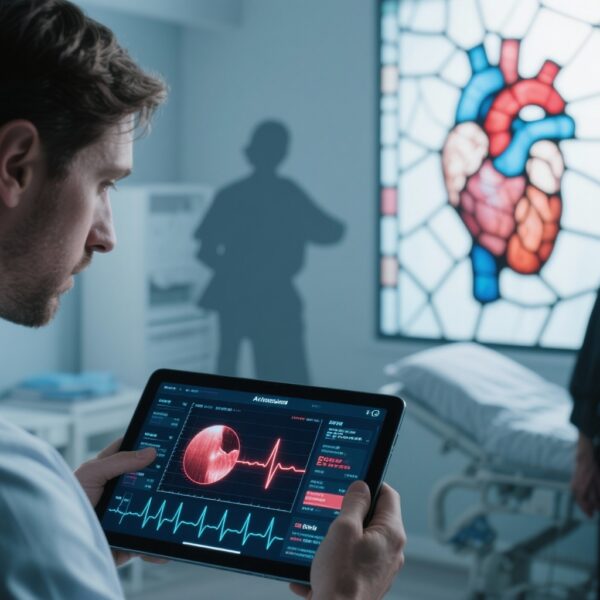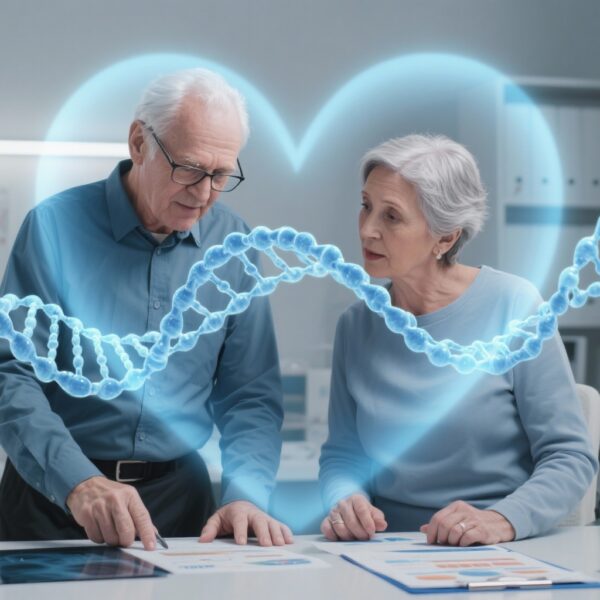ハイライト
– 長期コロナによる認知症状に対するリモート介入の第2相5群無作為化臨床試験(RECOVER-NEURO)では、適応型コンピュータ認知訓練、構造化認知行動リハビリテーションプログラム、または訓練と組み合わせたtDCSが主要評価項目(改良版日常生活認知スケール2)に対して差異のある利益を示さなかった。
– 5つのグループすべて(有効な比較対照群と偽処置対照群を含む)は時間とともに僅かなグループ内改善を示したが、グループ間調整後の差異は信頼区間が狭く、有意ではなかった。
– 介入は安全で、治療に関連する重篤な有害事象はなかった。本試験は、COVID-19後の主観的な認知苦情の治療における課題を強調し、将来のメカニズム研究や実践的な試験の優先事項を示している。
背景:臨床的文脈と未充足の需要
持続性の認知苦情(一般的に「脳霧」と表現され、注意、情報処理速度、記憶、実行機能の問題)は、SARS-CoV-2感染の急性後遺症(PASCまたは「長期コロナ」)の中心的な成分である。これらの症状は数ヶ月にわたり持続し、仕事、日常活動、生活の質に大きな機能的な影響を与える可能性がある。認知後遺症の高頻度にもかかわらず、エビデンスに基づく治療法は限られており、医師や患者にとって重要な未充足の需要となっている。
複数の治療戦略が提案されており、注意と情報処理速度を対象とするコンピュータ認知訓練プラットフォーム、脳卒中や頭部外傷のパラダイムから適応された構造化認知リハビリテーションプログラム、経頭蓋直流刺激(tDCS)などの神経モデレーション技術が含まれる。これらのアプローチに関する先行データは、主に異質な集団(高齢者、軽度認知障害、神経リハビリテーション)から得られており、長期コロナへの適用性は不確かなものである。したがって、この集団における有効性と安全性を確立するためには、適切に設計された無作為化試験が不可欠である。
試験デザイン
RECOVER-NEURO第2相試験は、2023年8月17日から2024年6月10日の間に22施設で実施された5群無作為化臨床試験である。試験では378人をスクリーニングし、長期コロナに起因する認知症状を持つ328人の参加者を登録した。中央値年齢は48歳(四分位範囲37-58)、女性は73.5%、人種・民族構成は71.6%が白人、14.3%が黒人、4.6%がアジア人、15.9%がヒスパニックだった。
介入は10週間にわたって週5回リモートで提供された。参加者は5つの群のいずれかに無作為に割り付けられた:
- 適応型コンピュータ認知訓練(BrainHQ、Posit Science)。
- 構造化認知行動リハビリテーション(PASC-Cognitive Recovery、PASC-CoRE)とBrainHQの組み合わせ。
- 有効tDCSとBrainHQの組み合わせ(tDCS-有効 + BrainHQ)。
- 有効な比較対照群:非構造化コンピュータパズルとゲーム。
- 偽tDCSとBrainHQの組み合わせ(tDCS-偽 + BrainHQ)。
評価は、基線時、介入中盤、介入終了時(主要評価時点)、介入終了後3ヶ月で対面で行われた。予め指定された主要評価項目は、改良版日常生活認知スケール2(ECog2)での参加者報告機能で、介入終了時と基線時の比較を行い、直近7日間を参照期間とした。二次評価項目には他の参加者報告指標と客観的な神経心理テストが含まれる。安全性と有害事象は全期間にわたって監視された。
主要な知見
10週間の介入期間終了時に、3つの有効な介入のいずれも、意図的に治療を受けた群において主要評価項目(改良版ECog2)で統計的または臨床上有意な利益を示さなかった。
平均変化の調整後差(有効治療群 vs 比較群)と95%信頼区間は以下の通りだった:
- BrainHQ vs 有効な比較群(非構造化コンピュータゲーム):0.0(95% CI, −0.2 to 0.2)。
- PASC-CoRE + BrainHQ vs 有効な比較群:0.1(95% CI, −0.1 to 0.3)。
- tDCS-有効 + BrainHQ vs tDCS-偽 + BrainHQ:0.0(95% CI, −0.2 to 0.2)。
- PASC-CoRE + BrainHQ vs BrainHQ単独:0.1(95% CI, −0.1 to 0.3)。
二次参加者報告指標と客観的な神経心理テストも、治療群間で差異のある利益を示さなかった。重要な点として、5つの群すべてが改良版ECog2やいくつかの二次指標で時間とともに一定程度のグループ内改善を示したが、これらの変化は有効群と比較群または偽群の間で異なるものではなかった。
安全性:重篤な有害事象はなかった。リモートで提供されたBrainHQ訓練、構造化リハビリテーションセッション、tDCS(有効と偽)は、外来患者コホートにおいて一般的に良好に耐容された。
効果推定値の解釈
報告された信頼区間の精度(零を中心に狭い範囲)は、これらの特定の介入が本試験で提供された形態では大きな治療効果は期待できないことを示唆している。グループ間の差異が零に収束し、観察可能なグループ内の改善が示されていることは、非特異的効果(平均への回帰、時間経過による自然回復、プラシーボ/文脈効果、または特定の有効成分ではなく、構造化プログラムへの参加による関与や注意の恩恵)を示している可能性がある。
専門家コメント:強み、制限、および含意
試験の強みには、無作為化、複数施設の設計;複数の有効な偽比較群の包含;リモート提供による実世界の関連性;予め指定された参加者報告主要評価項目;多様性のある各施設;厳密な対面神経心理評価が含まれる。
これらの知見を広範な臨床実践に適用する際の制限点:
- 集団と症状の異質性:長期コロナは炎症、微小血管損傷、自律神経機能不全、運動不足、気分や睡眠障害など、複数の潜在的なメカニズムを持つ異質な症候群である。特定のサブグループが介入に反応する場合、異質な試験サンプルは利益の信号を希釈させる可能性がある。
- 表型と評価項目の選択:主要評価項目は10週間後の短期(7日間)自己報告に基づいていた。患者報告指標は臨床的に意味があるが、期待、気分、または非特異的要因によって影響を受ける可能性がある。客観的な神経心理テストでも利益は示されなかったが、試験バッテリーは長期コロナで影響を受ける多様な認知領域の微妙な変化を検出する感度が低い。
- 投与量と提供方法:介入は完全にリモートで、高頻度(週5回)で自己管理された。異なる投与量、長期の監督下リハビリテーション、対面とオンラインを組み合わせたモデル、または睡眠、段階的な運動、薬物療法などの多様な介入が異なる結果をもたらす可能性がある。
- 疾患からの時期:急性感染からの経過時間と認知症状の持続期間の中央値は要約に明記されていなかった。治療効果は慢性化に依存する可能性があり、早期または遅期の介入が異なる結果をもたらす可能性がある。
- 期待と対照群の選択:有効な比較群(非構造化コンピュータゲーム)は、認知関与、社会的接触(一部の群では)、行動活性化を提供し、改善に寄与した可能性があり、群間の差異を低減させた。
メカニズム的な含意:無効の知見は、特定のリハビリテーションアプローチや神経モデレーションパラダイムが長期コロナの明確に定義されたサブグループの患者に利益をもたらす可能性を否定していない。しかし、現在提供されている形態でのこれらの介入の広範な実装に対する熱狂を抑制し、反応性が最も高いバイオシグネチャーまたは臨床表型を特定するためのターゲットメカニズム研究の必要性を強調している。
臨床と研究のまとめ
医師向け:現時点で、この試験からは、適応型BrainHQ訓練、PASC-CoRE構造化認知リハビリテーションプログラム、またはtDCS(本研究で設定された形態)が、長期コロナの未選別の患者の自己報告認知症状の改善に役立つという高品質の無作為化証拠はない。症状管理、併存症への配慮(睡眠、気分、痛み、薬剤効果)、機能的サポート、共同意思決定が依然として重要である。
研究者と資金提供者向け:将来の試験では、生物学的または臨床表型による層別化、メカニズムバイオマーカー(神経画像、炎症マーカー、自律神経テスト)の組み込み、複合的な多様な介入の試験、異なる投与量/監督モデルの探索を考慮すべきである。サブグループ解析、長期フォローアップ、実践的な有効性デザインで検証力のある試験が特に有用となる。
結論
厳密に実施された第2相無作為化試験では、適応型コンピュータ認知訓練、構造化認知行動リハビリテーションプログラム、またはリモート提供されたtDCSが、長期コロナの自己報告認知症状に対して、有効または偽比較群よりも差異のある利益をもたらすことを示すことができなかった。安全性プロファイルは許容可能であった。これらの知見は、SARS-CoV-2感染後の認知後遺症の複雑さと、未選別の長期コロナ患者集団への認知訓練や神経モデレーションの広範な適用ではなく、メカニズムに基づいたターゲット治療研究の必要性を強調している。
資金提供と試験登録
試験登録:ClinicalTrials.gov 識別子: NCT05965739。
資金提供:詳細な資金提供と利益相反開示については主論文を参照のこと。試験はRECOVER-NEURO臨床試験グループによって実施された。全文作者と資金提供声明は、引用文献に記載されているJAMA Neurology出版物で利用可能である。
参考文献
Knopman DS, Koltai D, Laskowitz D, et al; RECOVER-NEURO Clinical Trial Group. Evaluation of Interventions for Cognitive Symptoms in Long COVID: A Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. 2025 Nov 10:e254415. doi:10.1001/jamaneurol.2025.4415. PMID: 41212544; PMCID: PMC12603944.
選択された背景文献:
- Nalbandian A, Sehgal K, Gupta A, et al. Post-acute COVID-19 syndrome. Nat Med. 2021;27(4):601–615.
- Groff D, Sun A, Ssentongo AE, et al. Short-term and long-term rates of post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection: a systematic review. JAMA Netw Open. 2021;4(10):e2128568.
- World Health Organization. A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus, 6 October 2021. WHO; 2021.