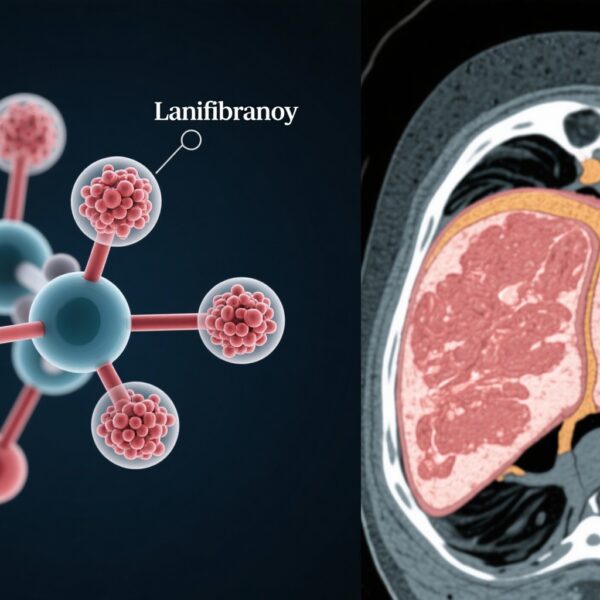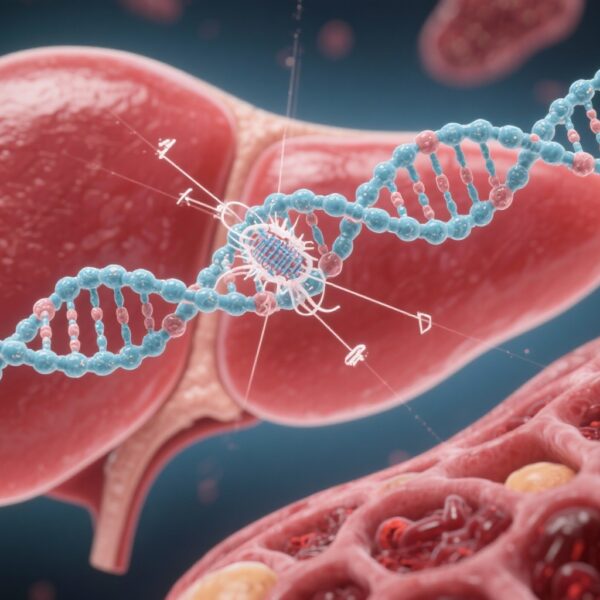ハイライト
- 最大限の医療管理下でも反復性肝性脳症(HE)を有する肝硬変患者において、FMTは安全で耐容性が高い。
- プラセボ群と比較して、FMTを受けた患者のHE再発率が有意に低下しました。用量、投与経路(カプセルまたは浣腸)、またはドナーの食事(菜食主義者対雑食主義者)に関係なく、HE再発率が減少しました。
- 基線時の腸内ラクノスポイラセア科の豊度が高いことや、ドナー由来の微生物叢の定着が成功したことが、HE再発の減少と生活の質の向上と関連していました。
研究背景と疾患負担
肝性脳症(HE)は、肝硬変の頻繁で障害を引き起こす神経精神症状であり、軽度の混乱から昏睡まで、認知機能障害が特徴です。これは、アンモニア代謝の障害、全身炎症、および腸内微生物叢の乱れ(dysbiosis)によって引き起こされる腸-肝臓-脳軸の多因子的な障害から生じます。現在の標準治療であるラクツロースやリファミシンによるアンモニア還元と細菌過増殖の対策にもかかわらず、HEの再発は一般的であり、予後を悪化させ、肝移植への適格性を制限します。この臨床的課題は、腸内微生物叢の平衡を回復し、HEの再発を予防する補助的な介入手段に対する未充足の医療ニーズを示しています。
初期試験の新規証拠は、健康なドナーの便を用いて微生物多様性を回復させるFMTが、認知機能を改善し、HEエピソードを減少させ得ることを示唆しています。しかし、最適な用量、投与経路、安全性、およびドナー選択はまだ確定されていません。THEMATIC試験は、厳密に設計された第II相無作為化、プラセボ対照、二重盲検試験でこれらの重要な問いに取り組んでおり、異なるドナーからのカプセルと浣腸で投与されるFMTの安全性と効果を評価しています。
研究デザイン
本試験では、肝硬変と既往歴のある明性HEを持つ60人の成人を対象とし、すべての参加者は安定したラクツロースとリファミシン療法を受けました。参加者は4つのグループ(各グループn=15)に等しく無作為に割り付けられ、3回の投与期間中に2つの経口カプセルと1つの浣腸を投与されました:
1. 3つの活性FMT用量
2. 2つの活性FMT用量と1つのプラセボ用量
3. 1つの活性FMT用量と2つのプラセボ用量
4. 3つのプラセボ用量
各被験者は、投与セッションごとに2つのカプセルと1つの浣腸を受け、その内容物はFMTまたはプラセボでした。ドナー便は、菜食主義者または雑食主義者の食事を摂っている個人から得られ、その影響を評価するために使用されました。フォローアップは介入後6ヶ月間続きました。
主要評価項目は、intention-to-treat原則を使用して、FMT関連の有害事象(AEs)と重篤な有害事象(SAEs)を評価する安全性でした。副次評価項目には、HE再発の発生率、全原因による入院、死亡、マイクロバイオームシーケンスによるドナー微生物叢の定着、および患者報告の生活の質(QoL)指標が含まれました。
主要な知見
安全性分析では、FMT関連の重篤な有害事象(SAEs)や有害事象(AEs)が見られず、用量数、投与経路、またはドナーの食事に関係なく耐容性が確認されました。全体的なSAEsと死亡率は統計的に治療群間で同等でした(SAEsのp=0.96;死亡率のp=1.0)。
6ヶ月以内のHE再発率は4つのグループ間で有意に異なりました(p=0.035, Cramer’s V=0.39)。事後解析では、全プラセボ群の再発率が最も高く40%であったのに対し、FMTを受けた群では有意に低い9%(オッズ比0.15, 95% CI 0.04–0.64)でした。重要的是、HE再発はFMT群間で用量(1〜3用量)、投与経路(カプセル対浣腸)、またはドナーの食事タイプに関係なく、有意に異なりませんでした。
生活の質は、有効な測定器具を用いて評価され、FMTを受けた患者群ではプラセボ群と比較して改善しており、生化学的コントロールを超えた症状の利益を示唆しています。
マイクロバイオーム分析では、ドナー由来の微生物叢の定着が主要なメカニズムの相関因子であることが明らかになりました。基線時の腸内ラクノスポイラセア科の豊度が高い患者は、ドナー由来の菌株の定着がより多く、HE再発リスクが低かったです。逆に、FMT前のラクノスポイラセア科の豊度が低い患者は、定着が減少し、HEの再発が増加しました。
専門家コメント
THEMATIC試験は、肝性脳症に対する微生物叢に基づく治療法の重要な探索を表しています。肝性脳症は、抗生物質や非吸収性二糖類以外に効果的な予防オプションが少ない疾患です。第II相無作為化、プラセボ対照、二重盲検設計は、結果の妥当性を強化し、翻訳可能性をサポートします。
免疫不全の肝硬変患者における感染リスクに関する懸念を考えると、FMT関連の安全性信号の欠如は安心材料です。経口と浣腸経路の効果の同等性は臨床的な柔軟性を提供し、ドナー間での同様の結果は、反応を左右するドナー微生物叢の特徴を解明するためのさらなる研究を必要とする興味深い点です。
注目すべきメカニズムの洞察は、ドナー微生物叢の定着を促進し、HE再発の予防に関連するラクノスポイラセア科の役割です。これは、腸内微生物代謝物とバリア機能が肝性脳症の病態生理に重要な役割を果たすという新規文献と一致しています。今後の研究では、ラクノスポイラセア科を患者選択や治療ターゲティングのバイオマーカーとして検証する可能性があります。
制限点には、サブグループ解析のための力が不足する比較的小規模なサンプルサイズ、短期フォローアップ期間、アンモニアレベルや炎症マーカーなどのメカニズムエンドポイントの欠如があります。ただし、これらの知見は、臨床効果を確認し、FMTプロトコルを最適化するための大規模な多施設試験への道を開きます。
結論
THEMATIC第II相試験は、FMTが最大限の標準治療を受けている肝硬変患者のHE再発を減らすための安全で潜在的に効果的な補助療法であることを確立しています。用量、投与経路、またはドナーの特性に関係なく、安全性プロファイルは良好でした。特に、FMTを受けた患者はプラセボ群と比較してHE再発率が低く、生活の質が改善しました。ラクノスポイラセア科を含む微生物叢の定着が、治療成功と関連していることが確認されました。
これらの知見は、HEに対する微生物叢ベースの介入の継続的な臨床開発を支持し、基線微生物シグネチャーを基にした個別化アプローチの必要性を強調しています。FMTや関連する微生物叢調整戦略を日常臨床に組み込むことで、この肝硬変の難治性合併症の管理が大きく変わる可能性があります。
参考文献
Bajaj JS, Fagan A, Gavis EA, Sterling RK, Gallagher ML, Lee H, Matherly SC, Siddiqui MS, Bartels A, Mousel T, et al. Microbiota transplant for hepatic encephalopathy in cirrhosis: The THEMATIC trial. J Hepatol. 2025 Jul;83(1):81-91. doi:10.1016/j.jhep.2024.12.047. Epub 2025 Jan 10. PMID: 39800192.
Vilstrup H, Amodio P, Bajaj J, Cordoba J, Ferenci P, Mullen KD, et al. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 2014 practice guideline by AASLD and EASL. Hepatology. 2014;60(2):715-735. doi:10.1002/hep.27210.
Kelly CR, Ihunnah C, Fischer M, et al. Fecal microbiota transplant for treatment of Clostridium difficile infection in immunocompromised patients. Am J Gastroenterol. 2014;109(7):1065-1071. doi:10.1038/ajg.2014.131.