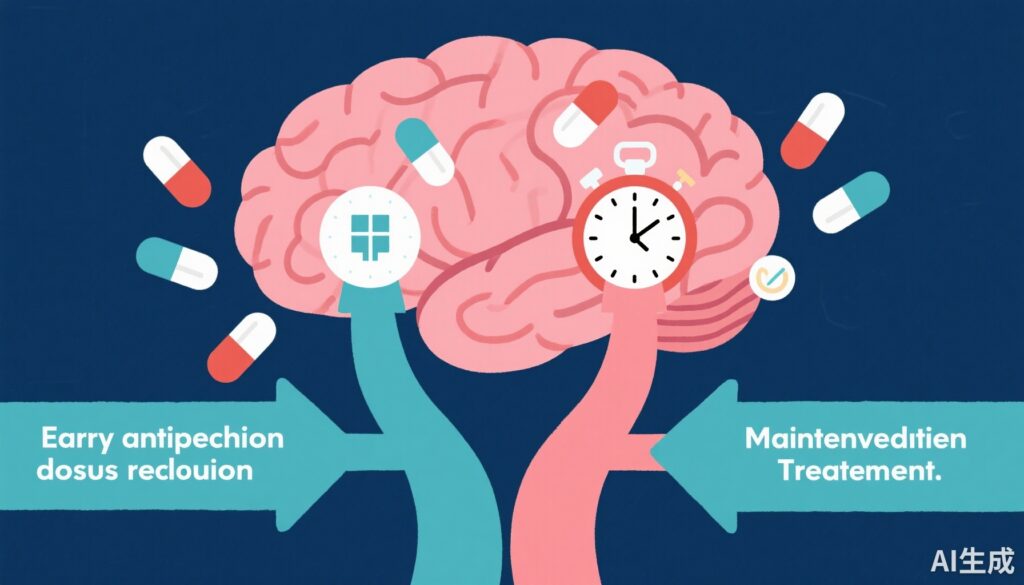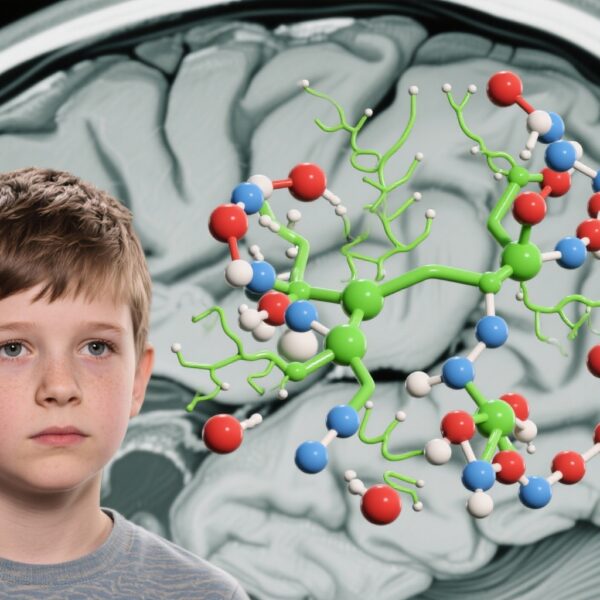ハイライト
– 初回発症精神病(FEP)寛解後12ヶ月以内の早期用量削減または中止(DRD)は、短期的な再発リスクを著しく高め、生活の質を低下させる。
– 4年間でDRD群と維持治療群の患者評価機能(WHODAS-2)に有意差はなかった。
– 3年目と4年目では、DRD群の研究者評価グローバル機能(GAF)が優れ、症状の重症度も改善傾向が見られた。
– 両群とも重篤な有害事象の発生率は同等だったが、自殺死亡はDRD群で数多く見られた。
研究背景と疾患負担
初回発症精神病(FEP)は、統合失調症スペクトラムおよび関連精神病の経過において重要な段階を示している。従来の臨床ガイドラインでは、寛解後に抗精神病薬の継続使用を推奨しており、再発リスクを最小限に抑えることが求められている。再発は予後不良、社会的機能障害、死亡率増加と強く関連しているためである。しかし、抗精神病薬の長期使用には代謝障害、神経学的副作用、脳容積減少などのリスクも伴う。
早期用量削減または中止(DRD)が副作用の軽減と心理社会的回復の促進により、機能的アウトカムの改善につながるかどうかについては議論が分かれている。これまでの長期研究では結果が不一致であり、早期再発リスクと潜在的な長期的機能的ベネフィットのバランスは解決されていない。したがって、短期的および長期的アウトカムを検討する大規模なプラグマティックな無作為化比較試験が、臨床判断のための情報提供に不可欠である。
研究デザイン
Handling Antipsychotic Medication Long-Term Evaluation of Targeted Treatment (HAMLETT) 研究は、2017年9月から2023年3月までオランダの26の専門精神病単位で実施されたプラグマティックな単盲検無作為化臨床試験(1:1割り当て)である。対象者は、初回精神病発症後の寛解を達成した患者で、外来と入院サービスの両方から募集された。
参加者は、寛解後12ヶ月以内に早期用量削減または中止(DRD)を開始する群か、12ヶ月間の維持抗精神病薬治療群に無作為に割り当てられた。試験は、無作為化後最大4年間追跡された。
主要アウトカムは、World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS-2) による患者評価機能である。二次アウトカムには、研究者評価グローバル機能(GAF)、生活の質指標、再発の発生、Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) による症状の重症度、重篤な有害事象(SAEs)や副作用などの安全性アウトカムが含まれている。
主要な知見
合計347人の患者が対象となり(男性69.5%、平均年齢27.9歳)。そのうち168人がDRD群、179人が維持治療群に割り当てられた。
主要アウトカム – 患者評価機能: WHODAS-2スコアは、時間と治療条件の間に有意な相互作用を示さなかった。これは、4年間の追跡期間中にDRD群と維持治療群の患者が認識する障害/機能に差がないことを示している。
1年目の再発と生活の質:早期DRDは、最初の1年間で再発リスクが著しく高まる(OR 2.84;95% CI, 1.08–7.66;P = .04)ことが確認された。さらに、DRD群の患者はこの期間中に生活の質が低いと報告していた(β = -3.31;95% CI, -6.34 to -0.29;P = .03)。これは、短期的な脆弱性を強調している。
3年目と4年目の長期的機能と症状:非線形の時間効果が現れ、DRD参加者は3年目(β = 3.61;95% CI, 0.28–6.95;P = .03)と4年目(β = 6.13;95% CI, 2.03–10.22;P = .003)で維持治療群よりも有意に高いGAFスコアを示した。4年目にはPANSSによる症状の重症度が改善する傾向も見られ(P for trend = .06)、症状管理と機能回復に一部の利点があることを示唆している。
安全性と有害事象:全体的には、重篤な有害事象や一般的な副作用の発生率は両群で同等だった。しかし、DRD群では自殺死亡が3件確認され、維持治療群では1件だった。件数は少ないものの、この結果は慎重な患者モニタリングの必要性を強調している。
1年後の薬物用量同等性:1年以降、抗精神病薬の用量は両群で有意に異ならなかった。これは、DRD患者の観察された長期的機能的ベネフィットが単なる薬物用量の違いによるものではないことを示唆している。著者らは、DRDが精神病脆弱性の管理に学習経験を提供し、患者が薬物使用決定をより自立的に行うことを可能にする可能性があると仮説を立てている。
専門家のコメント
HAMLETT試験は、初回発症精神病管理における重要な臨床的ジレンマ、つまり再発リスクと機能回復のバランスについて実用的なデータを提供している。その結果は、早期抗精神病薬用量削減が短期的な再発リスクを大幅に高めることを実証しており、寛解後の維持治療を推奨するガイドラインの警告を補強している。
ただし、後期の時間点での研究者評価機能の改善と症状傾向の複雑さは、戦略的かつ慎重に監督されたDRDが長期的には機能的な利点をもたらす可能性があることを示唆している。
しかし、DRD群での自殺死亡の増加は件数が少ないにもかかわらず、臨床応用における警戒を必要とする。これにより、個別化されたリスク分類、包括的な心理社会的支援、厳格な再発モニタリングが、用量削減を検討する場合に不可欠であることが強調されている。
制限点には、単盲検デザインにより期待バイアスが導入される可能性と、男性の比率が高いことで一般化に影響を与える可能性がある。今後の研究では、成功したDRDの予測因子を調査し、患者の好みと心理社会的介入を統合して結果を最適化することを目指すべきである。
結論
HAMLETT無作為化臨床試験は、初回発症精神病寛解後の早期抗精神病薬用量削減または中止が短期的な再発リスクを高め、1年目までの生活の質を低下させることを明確に示している。しかし、3年目から4年目には、この戦略は同等の薬物用量から1年目以降でも、より良い研究者評価グローバル機能と症状管理の改善傾向をもたらす可能性がある。
これらのデータは、再発と悪性事象の短期的リスクを、潜在的な長期的機能的ベネフィットと慎重に天秤にかけることの臨床的重要性を強調している。早期抗精神病薬中止は、単純な薬物用量の低下ではなく、患者をエンパワーメントする複雑なプロセスであり、個別化された臨床判断、構造化された支援、監視が必要である。
全体として、本研究は、初回発症精神病後の抗精神病薬管理に関する継続的な議論とガイドラインを支援し、安全性を優先しつつ長期的な回復の可能性を排除しない洗練されたアプローチを支持している。
参考文献
Sommer IE, de Beer F, Gangadin S, de Haan L, Veling W, van Beveren N, Boonstra N, Rosema BS, van Os J, Kikkert M, Koops S, Noorman J, Thielen F, Wijnen B, Begemann M; HAMLETT-OPHELIA Consortium. Early Dose Reduction or Discontinuation vs Maintenance Antipsychotics After First Psychotic Episode Remission: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2025 Oct 1. doi:10.1001/jamapsychiatry.2025.2525. Epub ahead of print. PMID: 41032294.
Leucht S, Tardy M, Komossa K, et al. Maintenance treatment with antipsychotic drugs for schizophrenia: meta-analysis of randomized controlled trials. Schizophr Bull. 2012;38(5): 1059–1072. doi:10.1093/schbul/sbs055.
Kane JM, Leucht S, Carpenter D. The Expert Consensus Guideline Series: Treatment of Schizophrenia. J Clin Psychiatry. 2003;64 Suppl 12:3-80.