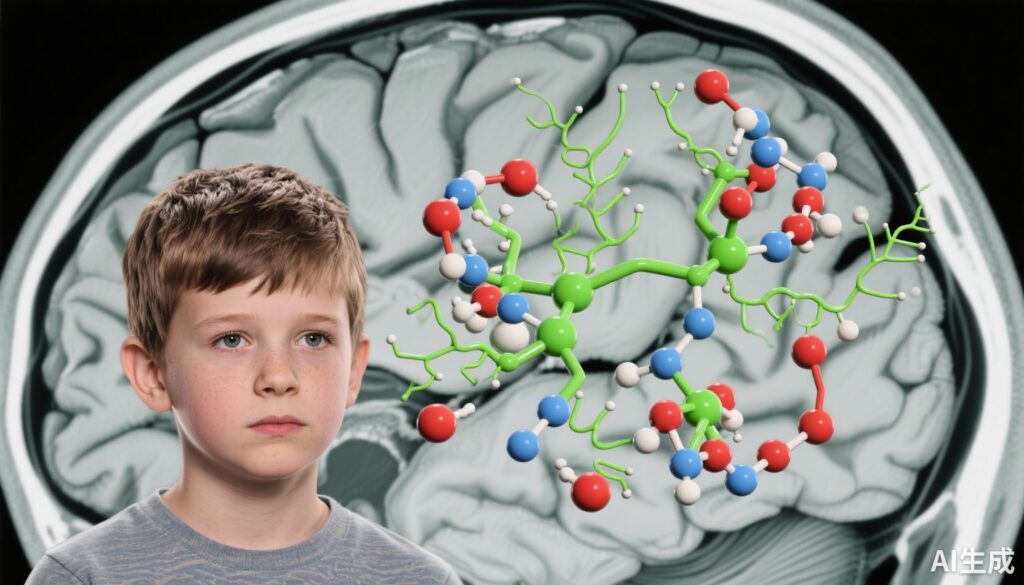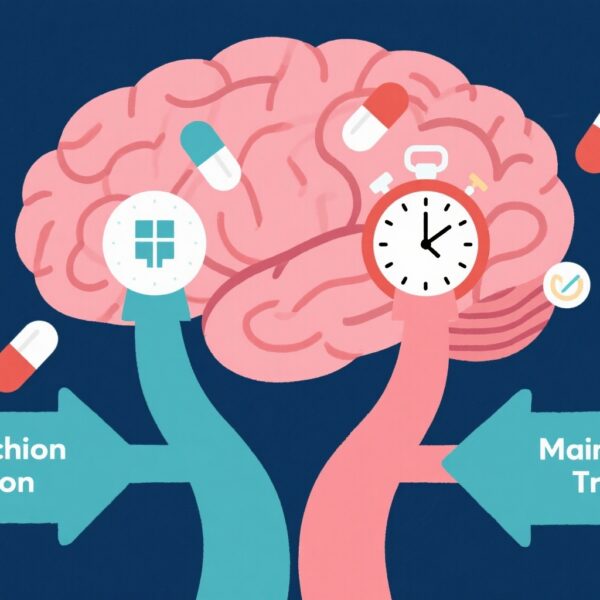ハイライト
この無作為化臨床試験では、メマンチンの自閉スペクトラム障害(ASD)の若者における社会機能障害に対する安全性と有効性を評価し、プラセボと比較して社会応答性に有意な改善が見られました。プロトン磁気共鳴分光法(1H-MRS)により、前帯状皮質(pgACC)でのグルタミン酸レベル上昇がメマンチン治療反応の潜在的な予測バイオマーカーであることが明らかになりました。
研究背景と疾患負荷
自閉スペクトラム障害(ASD)は、社会コミュニケーションと相互作用の持続的な困難、および制限的かつ反復的な行動を特徴とする神経発達障害です。社会機能障害は、影響を受けた個人が長期的な障害と生活の質の低下を経験する主因となっています。行動介入の進歩にもかかわらず、ASDの社会的欠陥を対象とした薬理学的治療は効果が限定的で一貫性に欠けています。グルタミン酸系神経伝達の異常がASDの病態生理に影響を及ぼしていることが示唆されており、プロトン磁気共鳴分光法(1H-MRS)研究では、社会認知と感情調節に関与する前帯状皮質(pgACC)などの主要な脳領域でのグルタミン酸レベルの変化が報告されています。これらの神経化学的な変化は、標的治療とバイオマーカーの開発の機会を提供し、個別化された治療と結果の最適化を可能にします。
研究デザイン
この研究は、2015年1月から2018年7月まで、学術機関で実施された12週間のプラセボ対照、二重盲検、並行設計の無作為化臨床試験でした。知的障害(IQ≥85)のないASDと診断された8歳から17歳の若者42人が参加し、外来精神科クリニックから募集されました。参加者は、グルタミン酸受容体拮抗薬であるメマンチン(グルタミン酸系シグナル伝達を調節すると仮定される)またはプラセボを投与されるように無作為に割り付けられました。最大用量は耐容性に基づいて1日20 mgまで徐々に増量されました。1H-MRSスキャンを使用して、健康な対照群が基準データを提供し、前帯状皮質(pgACC)でのグルタミン酸レベルを測定しました。主要なアウトカムは、社会応答性尺度第2版(SRS-2)総得点の25%以上の減少と、医師によるASD特異的なアンカーを使用した臨床全体的印象-改善(CGI-I)スコア2以下を組み合わせたものです。二次アウトカムには、安全性、耐容性、およびpgACCグルタミン酸レベルと治療反応の関係が含まれ、受信者操作特性(ROC)曲線分析を通じて評価されました。
主要な知見
合計42人の若者が治療を開始し(平均年齢13.2歳、76.2%が男性)、35人が意図治療効果分析に含まれ(16人メマンチン、19人プラセボ)、33人が試験を完了しました(16人メマンチン、17人プラセボ)。メマンチン治療は、プラセボと比較して有意に高い反応率を示しました:56.2%(16人中9人)対21.0%(19人中4人)、オッズ比4.8(95% CI, 1.1–21.2;P = .03)。メマンチンは、プラセボと比較して有意な有害事象の増加なく、良好に耐容され、この集団での安全性が確認されました。
神経化学分析では、ASDの若者が健康な対照群と比較して有意に高い平均pgACCグルタミン酸レベルを示していました(95.5 IU 対 76.6 IU;標準化平均差-1.2;95% CI, -1.8 から -0.6;P < .001)。特に、対照群の平均値から1標準偏差以上高的なグルタミン酸レベルを示した74.0%のASD参加者において、メマンチン治療群の80.0%が治療に反応したのに対し、プラセボ群では20.0%でした(オッズ比16.0;95% CI, 1.8–143.2;P = .007)。ROC曲線分析により、異常なpgACCグルタミン酸レベルがメマンチン反応者の識別に非常に効率的なバイオマーカーであることが確認されました。
専門家コメント
この無作為化臨床試験は、知的障害のないASDの若者における社会機能障害を軽減するための標的薬理学的介入としてメマンチンの重要な証拠を追加しました。結果は、ASDの社会的欠陥に影響を与えるグルタミン酸系の不規則性を示唆する仮説を裏付けており、前帯状皮質(pgACC)でのグルタミン酸レベルを用いた精密医療アプローチの重要性を強調しています。二重盲検プラセボ対照設計と主観的・客観的アウトカム指標の組み合わせにより、結果の妥当性が強化されました。
制限点としては、サンプルサイズが比較的小さいことと、12週間という比較的短い期間が挙げられます。これにより、長期的な有効性や安全性の評価が制約されます。より大規模なコホートと長期フォローアップを含む将来の研究が必要であり、治療効果の持続性を確認し、多様なASD現象型におけるメマンチンの影響を探索することが求められます。また、知的障害のあるASD若者への一般化可能性は未確定です。それでも、この研究は、ASDの生物学的サブタイプ化と個別化された介入の重要な一歩を表しており、未解決のニーズに対処するための神経化学ガイド治療戦略のさらなる研究を奨励します。
結論
メマンチンは、知的障害のないASDの若者における社会機能障害を軽減するための耐容性が高く効果的な選択肢です。前帯状皮質(pgACC)でのグルタミン酸レベルの上昇は、ASDの神経化学的特徴を特徴づけるだけでなく、メマンチン治療に最も利益を得られる個人を特定する役割も果たします。これらの結果は、臨床決定プロセスにおけるグルタミン酸系バイオマーカーの導入を支持し、ASD管理における未解決のニーズに対処するための神経化学ガイド治療戦略のさらなる研究を奨励します。
参考文献
Joshi G, Gönenc A, DiSalvo M, Faraone SV, Ceranoglu TA, Yule AM, Uchida M, McDougle CJ, Wozniak J. メマンチンによる自閉スペクトラム障害の若者の社会機能障害の治療:無作為化臨床試験. JAMA Netw Open. 2025年10月1日;8(10):e2534927. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2025.34927. PMID: 41032298.
試験登録:ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01972074.
関連文献:Veenstra-VanderWeele J, Warren Z. 正常発達の文脈における介入:自閉症からの洞察. Nat Rev Neurosci. 2015;16(9):592-605. doi:10.1038/nrn3984
Moses LM, et al. 自閉スペクトラム障害におけるグルタミン酸受容体の不規則性:治療への影響. Pharmacology & Therapeutics. 2020;211:107540.