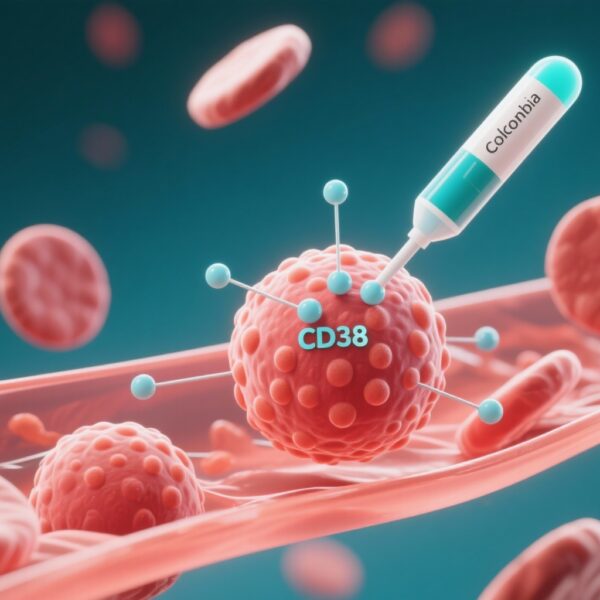ハイライト
– 胎児期から生後1000日間の砂糖配給制限に曝露された人々は、成人期の複数の心血管アウトカムが20-30%減少しています。
– この研究では、1953年の砂糖配給終了時期を活用した英国の出生コホートを使用して、自然実験を行いました。
– 糖尿病と高血圧が、早期砂糖制限による心血管リスク低減の一部を媒介しています。
– 心臓磁気共鳴画像(MRI)検査では、早期砂糖制限に曝露された人々の左室駆出量と射血分数に微小な改善が見られました。
研究背景
心血管疾患(CVD)は、遺伝子、ライフスタイル、早期生活環境の複雑な相互作用により、世界中で最も主要な死亡原因の一つとなっています。最近の証拠は、胎児期から生後2年間の最初の1000日間における栄養暴露が、将来の心血管リスクをプログラムする重要な期間であることをますます認識しています。過剰な食事性砂糖摂取は、肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの主要なリスク因子の発症に関与しており、これらはすべてCVDの前駆症状です。
しかし、早期生活での砂糖制限と成人期心血管アウトカムとの直接的な長期的関連を示す証拠は、数十年にわたる栄養暴露の評価における困難さから、ほとんどありませんでした。第二次世界大戦中および戦後の英国の砂糖配給政策が提供する自然実験は、この重要な初期発達期における砂糖摂取の調整が心血管に及ぼす長期的影響を準実験的に検討する機会を提供しています。
研究デザイン
この大規模な英国人口ベースのコホート研究では、1951年10月から1956年3月に生まれた63,433人のUK Biobank参加者を対象としました。これは、戦後砂糖配給が1953年半ばに終了するまでの最後の数年間を含む期間です。研究者は、配給終了時期に対する出生日の相対的な位置付けに基づいて曝露を割り当て、これを自然実験として扱いました。
基線で既存の心血管疾患、多胎児、養子縁組、外国出生の参加者は除外され、混在要因を減らすために対象外とされました。外部検証コホートには、米国のHealth and Retirement StudyとEnglish Longitudinal Study of Ageingのデータが含まれており、一般化可能性を強化しています。
主なエンドポイントは、心血管イベントの発症率:CVD診断、心筋梗塞、心不全、心房細動、脳卒中、CVD死亡率であり、リンクされた国民保健記録によって確認されました。研究では、人口統計学的、社会経済学的、ライフスタイル、親の健康、遺伝学的、地理的要因を調整したCox比例ハザードモデルとパラメトリックハザードモデルを使用して、早期砂糖制限曝露の効果を分離しました。
サブセットでは、心臓磁気共鳴画像(MRI)検査が行われ、早期生活曝露によって潜在的に説明される心臓の構造的および機能的違いが定量されました。
主要な知見
中心的な知見は、胎児期から生後1000日間の砂糖配給制限への曝露期間と成人期心血管リスクとの間に、段階的逆関係があるということでした。胎児期から生後1年から2年間まで砂糖制限に曝露された参加者は、曝露されていない参加者と比較して、すべての評価された心血管アウトカムのハザード比が有意に1未満でした:
- 心血管疾患:HR 0.80 (95% CI 0.73–0.90)
- 心筋梗塞:HR 0.75 (95% CI 0.63–0.90)
- 心不全:HR 0.74 (95% CI 0.59–0.95)
- 心房細動:HR 0.76 (95% CI 0.66–0.92)
- 脳卒中:HR 0.69 (95% CI 0.53–0.89)
- 心血管死亡率:HR 0.73 (95% CI 0.54–0.98)
これらの関連は、潜在的な混在要因を広範に調整した後も持続しました。媒介分析では、新規発症の糖尿病と高血圧が約31.1%の保護効果を説明していることが示され、過剰な砂糖摂取の既知の代謝結果と一致していました。出生体重は、しばしば胎児期の栄養状態の指標となることが多いですが、2.2%の媒介しか説明できなかったため、生後砂糖摂取制限が主導的な役割を果たしていると考えられます。
サブグループの心臓MRI検査結果では、曝露群の心機能指標に微小だが統計的に有意な改善が見られました。左室駆出量指数は0.73 mL/m²増加し、射血分数は0.84%向上し、数十年後に心臓のポンプ効率が向上している可能性を示唆しています。
異なる人口特性と環境を持つ外部コホートでの検証分析は、知見の堅牢性と再現性を支持しました。
専門家のコメント
この研究は、稀な自然実験を巧妙に活用し、早期栄養環境、特に砂糖の可用性と生涯心血管健康との間の持続的な関連を提供します。これらの知見は、健康と疾患の発生学的起源(DOHaD)理論と一致し、早期栄養の調整がCVD予防戦略として支持されています。
このような長期曝露に対するランダム化比較試験を実施することは実現不可能ですが、広範な混在要因を調整した準実験設計と外部検証コホートの使用は、因果推論を強化しています。ただし、測定されていない環境的または行動的要因による残存混在は完全には排除できません。
生物学的根拠は、過剰な砂糖摂取がインスリン抵抗性、肥満、高血圧を促進し、これらが心血管リスクの中心的な役割を果たすことが知られていることで支持されています。微小な心臓MRI変化は、早期砂糖制限がリスク因子の媒介を超えて直接的な心筋的利益をもたらす可能性があることを示唆しています。
今後の研究では、エピジェネティクスや代謝プロファイリングを通じて分子メカニズムを探索し、現代の設定において早期生活における食事性砂糖制限が同様の利益をもたらすかどうかを評価する必要があります。
結論
胎児期から生後1000日間の砂糖配給制限への曝露は、成人期の主要な心血管イベントと死亡率のリスクを大幅に低下させ、心機能に微小な改善をもたらします。これらの知見は、早期生活栄養が生涯心血管健康に及ぼす重要な影響を強調し、早期発達期における過剰な砂糖摂取を制限する公衆衛生戦略を支持しています。
資金源と試験登録
元の研究は、UK Biobankと適切な政府保健研究資金機関の支援を受けました。これは観察的な自然実験であるため、臨床試験の登録は適用されません。
参考文献
1. Zheng J, Zhou Z, Huang J, Tu Q, Wu H, Yang Q, Qiu P, Huang W, Shen J, Yang C, Lip GYH. 出生後1000日間の砂糖配給曝露と長期的心血管アウトカム:自然実験研究. BMJ. 2025 Oct 22;391:e083890. doi: 10.1136/bmj-2024-083890. PMID: 41125420; PMCID: PMC12542096.
2. Gluckman PD, Hanson MA. 疾病の発生学的起源のパラダイム:機序と進化的視点. Pediatr Res. 2004 May;56(3):311-7.
3. Malik VS, Hu FB. 砂糖入り飲料と心臓・代謝健康:最新の証拠. Nutrients. 2019 Aug 9;11(8):1840.
4. Barker DJ. 成人期疾患の発生学的起源. J Am Coll Nutr. 2004 Dec;23(6 Suppl):588S-595S.