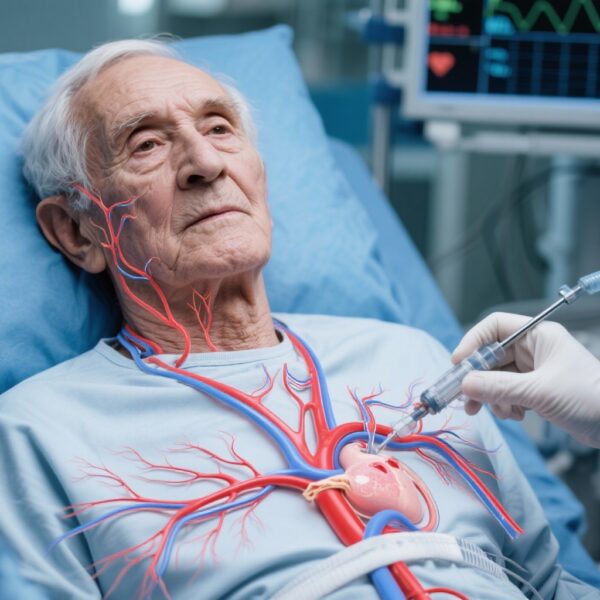ハイライト
- 疑いのある冠動脈疾患(CAD)を有する安定した症候性患者において、初期検査として機能的ストレステストまたは解剖学的冠CTAを使用した場合、10年間の全原因死亡率に差は見られませんでした。
- 心血管死亡率の傾向は冠CTAに有利でしたが、統計的有意性には達しませんでした。
- 冠CTAで軽度の非閉塞性CADを含むいかなる異常も見つかると、死亡リスクが大幅に予測されましたが、ストレステストでのみ重度の異常が死亡を有意に予測しました。
- ガイドラインに基づく医療療法(スタチン、βブロッカー、抗血小板薬)は、初期検査戦略による死亡結果を変更しませんでした。
研究背景と疾患負担
冠動脈疾患(CAD)は世界中で依然として主要な死亡および障害の原因です。胸痛や呼吸困難などの症状を呈する患者は、しばしば非侵襲的な検査を受けてCADの評価が行われます。主に2つの診断戦略が用いられます:ストレステスト(運動または薬理学的)による機能的評価と、冠CTAによる解剖学的視覚化です。ストレステストは心筋虚血を評価し、CTAは冠動脈の解剖学的構造とプラーク負荷を示します。現在の臨床ガイドラインでは両方のアプローチが推奨されていますが、初期検査選択の長期予後の影響については不確かな点があります。PROMISE(胸部疼痛評価のための前向き多施設画像検査試験)は、症候性患者を初期CTAとストレステストに無作為に割り付け、これらの診断戦略の長期結果を比較するための貴重なデータセットを提供しています。疑いのあるCADの症状評価は高頻度の臨床シナリオであるため、初期検査選択が生存率や心血管イベントに与える影響を理解することは、患者管理や保健資源配分に重要です。
研究デザイン
この分析は、2009年から2014年にかけて北米の193の多専門外来施設で実施されたPROMISE無作為化対照試験の延長フォローアップ結果を報告しています。合計10,003人の疑いのあるCADを有する症候性患者が1:1の比率で初期冠CTAまたは機能的ストレステストに無作為に割り付けられ、その後の管理は通常の診療に従って医師の裁量に任されました。
現在の2025年の分析では、2024年の全国死亡指数を使用して死亡を確認し、中央値10.6年(四分位範囲:9.9〜11.3年)、最大12.4年のフォローアップを拡大しています。
元々のPROMISEの主要エンドポイントは、全原因死亡、心筋梗塞、不安定狭心症の入院、または主要な手術合併症の複合エンドポイントでした。この延長フォローアップでは、全原因死亡が主要エンドポイントとなり、心血管死亡が二次エンドポイントとなりました。
主要な知見
ベースラインでは、参加者の平均年齢は61歳で、女性が若干多かったです(52.7%)。大多数の患者(87.6%)が胸痛または呼吸困難を呈していました。フォローアップ期間中に1,128件の死亡(14.4%)が発生し、CTA群(14.3%)とストレステスト群(14.5%)でほぼ等しく分割されました。CTAとストレステストを比較した全原因死亡の調整前のハザード比(HR)は0.98(95% CI, 0.87–1.10)で、有意な生存差は見られませんでした。
心血管死亡は、調整前のHR 0.84(95% CI, 0.67–1.05)、調整後のHR 0.89(95% CI, 0.41–1.94)でCTAに有利な傾向を示しましたが、統計的有意性には達しませんでした。これは解剖学的画像の可能性があるが確定的な利益を示唆しています。
サブグループ解析では、全原因死亡や心血管死亡に対する検査戦略と年齢(60歳未満または60歳以上)、性別、または人種/民族間の有意な相互作用は見られませんでした。
重要なことに、冠CTAで軽度の非閉塞性CAD、中等度、または重度の疾患を含むいかなるレベルの冠動脈異常も識別されると、正常なCTA結果と比較して、調整後のハザード比が1.99〜3.44(P < .001)と大幅に増加しました。一方、ストレステスト結果では、重度の異常のみが有意な死亡リスク増加(HR, 1.45; 95% CI, 1.10–1.91)をもたらしました。
90日を超えて生存した患者のランドマーク解析では、スタチン(相互作用P = .22)、βブロッカー(P = .76)、または抗血小板薬(P = .49)の使用と死亡結果との間に有意な相互作用は見られませんでした。
この延長フォローアップ解析は、CTAで検出された冠動脈異常、特に非閉塞性の場合でも、機能的テスト異常よりも生存に影響を与える閾値が低いことを強調しています。
専門家のコメント
PROMISE試験の延長データは重要なパラダイムを確立しています:疑いのある冠動脈疾患を有する安定した症候性患者における初期の機能的ストレステストと解剖学的冠CTAの選択は、10年間の全原因死亡率や心血管死亡率に影響を与えません。この結果は以前の短期解析と一致し、患者の好み、臨床像、利用可能性、コストの考慮に基づいた臨床判断を可能にします。
メカニズム的には、CTAは早期動脈硬化(非閉塞性プラークを含む)を検出する感度が高く、より精密なリスク層別化を可能にします。これがCTAのいかなる異常も死亡と相関する一方、ストレステストでは重度の虚血のみが予後的に有意である理由を説明しています。ただし、この改善されたリスク層別化が初期検査戦略に基づく生存差に直接反映されなかったことから、その後の臨床管理と二次予防療法が重要な役割を果たしていることが示唆されます。
制限点には、治療後の管理を担当する医師が調整できる実践的なデザインがあり、これにより検査選択に由来する生存影響の違いが希釈される可能性があります。また、異なる人口統計学的特性や症状プロファイルを持つ集団への一般化は慎重に行う必要があります。
スタチン、βブロッカー、抗血小板薬の使用と検査モダリティとの間の相互作用が死亡に及ぼさないことは、初期診断アプローチに関わらず、証拠に基づく二次予防が極めて重要であることを強調しています。
結論
疑いのある冠動脈疾患を評価する症候性患者において、初期非侵襲的検査として機能的ストレステストまたは解剖学的冠CTAを使用した場合、10年間の生存率は同等です。CTAで検出された冠動脈異常の予後予測力はその有用性を示していますが、初期検査として選択した場合、死亡率の優位性は得られません。したがって、検査に関する臨床的決定は、患者要因、地域の専門知識、リソースの考慮事項を統合し、長期生存に影響を与えることなく行うべきです。今後の研究では、解剖学的と機能的検査戦略の統合、またはCTA結果に基づく標的療法が診断を超えた臨床結果にどのように影響するかを探る可能性があります。
参考文献
1. Douglas PS, Stebbins A, Foldyna B, et al. Survival After Initial Stress Testing vs Anatomic Testing in Suspected Coronary Artery Disease: Long-Term Follow-Up of the PROMISE Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol. 2025 Aug 27:e252882. doi:10.1001/jamacardio.2025.2882.
2. Writing Committee Members, et al. 2021 AHA/ACC Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain. Circulation. 2021;144:e368-e454.
3. Min JK, et al. Prognostic Value of Coronary Computed Tomographic Angiography. J Am Coll Cardiol. 2019;73(18):2242–2258.