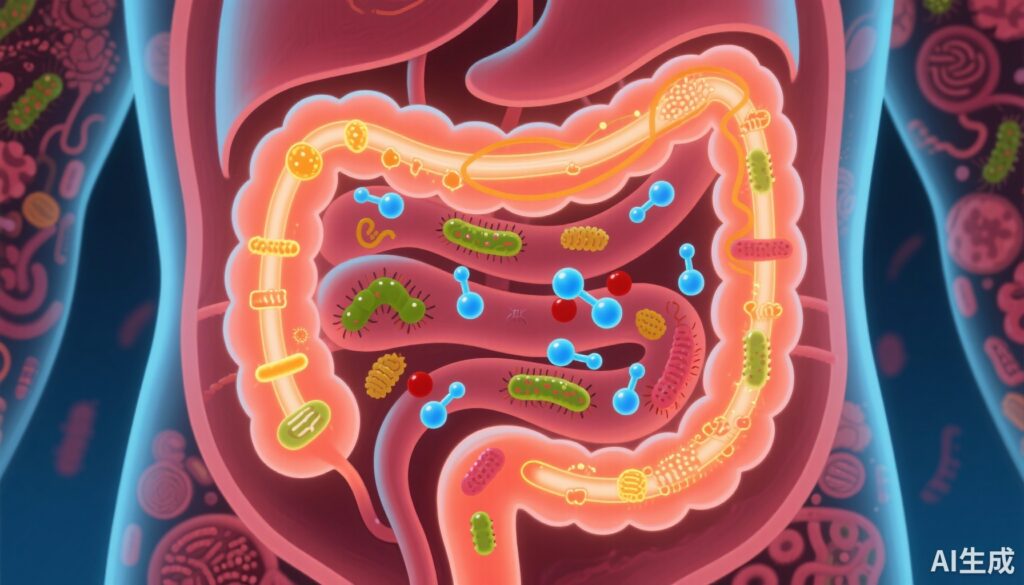研究のハイライト
この探索的ランダム化クロスオーバー試験により、短期間のエネルギー摂取量の変動が、糞便中のセロトニン濃度、腸内細菌由来のトリプトファナーゼ遺伝子の存在量、および可消化エネルギーや代謝可能エネルギーを含むエネルギー吸収パラメーターに著しい影響を与えることが明らかになった。具体的には、エネルギーの過剰摂取はエネルギー吸収の増加と関連していたが、それに反して糞便セロトニンとトリプトファナーゼの減少と関連していた。後者(トリプトファナーゼ)はバクテロイデス属(Bacteroides)の存在量と正の相関を示した。これらの発見は、エネルギー利用を調節し、代謝制御に影響を与えうる、動的な腸-微生物-宿主相互作用の存在を示唆している。
研究の背景と疾患の負荷
肥満およびその関連合併症を含む代謝性疾患の有病率の増加は、食事からのエネルギー摂取が宿主の代謝にどのように影響するかを理解することの重要性を浮き彫りにしている。腸内微生物叢は、その豊富な酵素プロファイル、特にトリプトファン代謝に関与するトリプトファナーゼ活性により、宿主のエネルギー恒常性(ホメオスタシス)における重要な調節因子として浮上している。主に腸内で産生されるセロトニンは、腸の運動、分泌、および全身の代謝プロセスに影響を与える。しかし、短期間の食事エネルギーの変動、腸内細菌の酵素機能(トリプトファナーゼ)、糞便セロトニンレベル、およびエネルギー吸収との間の関連性はいまだ不明確である。これらのメカニズムの連鎖を解明することは、栄養調節と代謝の健康に関する基本的な経路を明らかにする上で不可欠である。
研究デザイン
この探索的ランダム化クロスオーバー試験には、15名の健常な成人被験者が参加し、それぞれ8日間の3つの異なる食事介入(過剰摂取、対照(維持カロリー)、および摂取制限)を受けた。本研究では、エネルギー摂取量を体系的に変更し、それが腸内細菌の機能、糞便セロトニン、およびエネルギー吸収に与える急性影響を調査した。エネルギー吸収は、食事摂取量と糞便排出量をボンベ熱量計で測定した可消化エネルギーおよび代謝可能エネルギーによって定量化された。糞便セロトニン濃度は、液体クロマトグラフィー・タンデム質量分析法(LC-MS/MS)によって測定された。トリプトファナーゼ(EC 4.1.99.1)遺伝子を含む腸内微生物叢の構成および機能遺伝子の存在量は、16S rRNA遺伝子シーケンシングおよびメタゲノムショットガン解析によって評価された。吸収に影響を与える可能性のある生理学的パラメーターとして、腸管通過時間も測定された。
主要な発見
- エネルギー吸収と通過時間: 過剰摂取は可消化エネルギーを著しく増加させ(p < 0.001)、その値は対照条件よりも有意に高かった(p = 0.032)。代謝可能エネルギーと腸管通過時間も過剰摂取時に有意に増加し、対照条件(代謝可能エネルギー:p = 0.001;腸管通過時間:p = 0.014)および摂取制限条件(代謝可能エネルギー:p < 0.001;腸管通過時間:p = 0.004)と比較して、より高いエネルギー負荷下で栄養吸収効率が向上し、同時に腸の運動または輸送ダイナミクスが変化したことを示している。
- 糞便セロトニンレベル: 予想に反して、過剰摂取条件における糞便セロトニン濃度は、対照条件(p = 0.005)および摂取制限条件(p < 0.001)よりも有意に低かった。この逆相関関係は、エネルギー過剰状態において、腸内のセロトニンシグナルが下方制御される可能性を示唆しており、これは腸の運動、分泌、または吸収効率を調節するための適応メカニズムである可能性がある。
- トリプトファナーゼ遺伝子の存在量と微生物叢の構成: トリプトファナーゼ遺伝子の存在量は、食事条件間で有意に異なり(p = 0.0019)、過剰摂取条件では摂取制限条件よりも存在量が低かった(p = 0.001)。この酵素は、微生物がトリプトファンを分解してインドールおよびその関連代謝物を生成するために不可欠であり、すべての条件下でバクテロイデス属の存在量と強い相関関係(相関係数0.696–0.896)を示した。これは、バクテロイデス属が食事のエネルギー負荷に応答するトリプトファン代謝の主要な微生物貢献者であることを示している。
- セロトニンとエネルギー吸収の関連: 個人内変動の分析により、糞便セロトニンレベルと可消化エネルギー吸収との間に有意な負の相関(β = –0.077、p = 0.019)が示され、セロトニンレベルの低下が食事からのエネルギー抽出を促進する可能性が示唆された。
総じて、これらの結果は、短期的なエネルギー摂取が、協調的な方法で腸内細菌の機能と宿主の生化学的産物を調節し、栄養素の吸収効率に影響を与えうることを示している。
専門家のコメント
本研究は、食事摂取、腸内細菌の酵素活性、および宿主の代謝シグナル分子(セロトニンなど)との間に、迅速かつ動的な相互作用が存在することを示す説得力のあるエビデンスを提供している。エネルギー摂取量が増加したにもかかわらず糞便セロトニンレベルが低下したことは、食物摂取と腸内セロトニン産生を直接関連付ける単純なモデルに疑問を投げかけるものである。むしろ、カロリー過剰下で栄養吸収を最適化することを目的とした適応メカニズムが存在するという仮説を支持している。
過剰摂取状態におけるトリプトファナーゼ遺伝子の存在量の低下は、微生物群集の構造または代謝の優先順位が変化し、トリプトファン代謝に依存しないエネルギー抽出経路をより好むようになったことを反映している可能性がある。トリプトファナーゼとバクテロイデス属との間の強い相関は、先行研究と一致しており、栄養素処理における同属の柔軟性を強調している。
限界: サンプルサイズが小さいため一般化には限界があり、介入期間が短いため長期的な適応を理解することはできない。さらに、糞便測定は遠位腸のプロセスを代表するものであり、近位腸での事象を完全には捉えきれない可能性がある。研究デザインは因果関係を確立するものではないが、さらなるメカニズム研究に値する重要な相関パターンを示している。
結論
短期的な食事エネルギー負荷は、糞便セロトニンレベル、腸内細菌のトリプトファナーゼ遺伝子の存在量、およびエネルギー吸収指標に顕著な影響を与え、宿主の代謝を調節する緊密に相互接続されたネットワークの存在を示唆している。これらの発見は、エネルギーバランスと代謝の健康を最適化するための潜在的な治療標的として、腸内微生物叢とセロトニン経路を調節する可能性を切り開くものである。今後の研究では、縦断的効果、多様な集団、および微生物代謝と宿主生理学を統合するメカニズム経路を探求すべきである。
参考文献
Yoshimura E, Hamada Y, Hatamoto Y, Nakagata T, Nanri H, Nakayama Y, Iwasaka C, Hayashi T, Suzuki I, Ando T, Ishikawa-Takata K, Tanaka S, Ono R, Araki M, Kawashima H, Chen YA, Park J, Hosomi K, Mizuguchi K, Kunisawa J, Miyachi M. Effect of short-term dietary intervention on fecal serotonin, gut microbiome-derived tryptophanase, and energy absorption in a randomized crossover trial: an exploratory analysis. Gut Microbes. 2025 Dec;17(1):2514137. doi: 10.1080/19490976.2025.2514137 IF: 11.0 Q1 . Epub 2025 Jun 9. PMID: 40488306 IF: 11.0 Q1 ; PMCID: PMC12150606 IF: 11.0 Q1 .