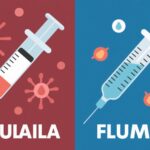ハイライト
- ダルベポエチンは、早産児の赤血球量を著しく増加させ、輸血の頻度とドナーへの曝露を減少させた。
- プラセボ群と比較して、補正年齢22-26ヶ月での神経認知機能の改善は認められなかった。
- 早産網膜症などの主要な有害事象の発生率は、ダルベポエチン群で増加しなかった。
- ダルベポエチンは、中等度または重度の慢性肺疾患のリスクを低下させた。
研究背景と疾患負担
早産は、世界中の重大な健康課題であり、全出生の10%以上に影響を与えている。特に、29週未満で生まれる極端な早産児は、医原性血液喪失、未熟な赤血球生成、および重篤な病態により、頻繁に赤血球輸血を必要とする。複数回の輸血は、これらの乳児をドナー血液に曝露し、感染、免疫反応、そして長期的な神経発達への影響のリスクを伴う。さらに、早産児は脳の未成熟さと周産期合併症により、神経発達障害のリスクが高まっている。観察研究や小規模な無作為化試験では、エリスロポエチン(EPO)やその類似体であるダルベポエチンなどの赤血球生成刺激剤(ESA)が、輸血の必要性を軽減し、神経発達の結果を改善する可能性があることが示唆されているが、十分な検証力を持つ堅固な試験は不足している。
研究デザイン
本研究は、19の米国新生児研究ネットワークセンター、33の新生児集中治療室で実施された多施設、二重盲検、プラセボ対照の無作為化試験である。23 0/7週から28 6/7週の胎齢で生まれた乳児が対象となり、出生後36時間以内に登録された。参加者は、週1回の皮下ダルベポエチン(10 μg/kg)または同一のプラセボを受け、35週の月経後齢まで投与された。すべての乳児は標準的な鉄剤補給と輸血プロトコルを受けた。主評価項目は、補正年齢22-26ヶ月で評価されたベイリー乳児発達スケール第3版(Bayley-III)の平均認知合成スコアであった。評価前に死亡した乳児には、最低の可能なスコアが割り当てられた。主な副次評価項目には、輸血曝露、赤血球量、ドナー曝露、慢性肺疾患(BPD)、早産網膜症(ROP)の発生率が含まれた。安全性評価項目には、有害事象のモニタリングが含まれた。
主要な知見
合計650人の乳児が無作為化された(ダルベポエチン群322人、プラセボ群328人)、平均胎齢26.2週。主評価項目は、集団の90%(583人)で利用可能であった。
神経認知機能の結果:
ダルベポエチン群の平均(SD)Bayley-III認知合成スコアは80.7(19.5)で、プラセボ群は80.1(18.7)であった。調整後の平均差は-0.23(95% CI, -3.09 to 2.64)で、統計的または臨床上の有意な差は認められなかった。したがって、この用量と投与スケジュールでのダルベポエチンは、補正年齢22-26ヶ月での認知機能の改善には寄与しなかった。
血液学的および輸血の結果:
– 病院滞在中に輸血なしで済んだ乳児の割合は、ダルベポエチン群で40%、プラセボ群で21%(調整後RR 1.3, 95% CI 1.2-1.5)であった。
– ダルベポエチン群の平均輸血回数は、プラセボ群の3.3(3.5)に対し2.3(3.1)と少なかった。
– ダルベポエチン群では、ドナーへの曝露が少ない(平均1.6対2.2ドナー)。
– 生後2週間時点で、ダルベポエチン群の乳児は、赤血球量(調整後平均差3.2, 95% CI 1.7-4.7)と平均ヘマトクリット値(2.8, 95% CI 2.1-3.6)が有意に高かった。
呼吸器および眼科の結果:
– 1級以上の慢性肺疾患のリスクは、ダルベポエチン群で低かった(35% vs 46%; RR 0.78, 95% CI 0.64-0.96)。
– 2段階以上の重症早産網膜症の発生率は、両群で類似していた(13% vs 16%)。
安全性:
両群間で有意な違いは認められず、この集団でのダルベポエチンの安全性が支持された。
専門家のコメント
この厳密に実施された多施設試験は、ダルベポエチンが極端な早産児の血液学的利点をもたらし、輸血の負担を軽減する一方で、幼児期の神経認知機能の改善には寄与しないことを強力に示している。これらの知見は、貧血の予防と輸血関連リスクの軽減がESA療法によって達成可能であるという仮説と一致しているが、神経保護はより複雑であり、単に赤血球量や酸素運搬能力だけに依存していない可能性がある。重症早産網膜症やその他の有害事象の増加が確認されなかったことは、ESAsと増殖性合併症に関する懸念が和らげられる。中等度-重度の慢性肺疾患のリスク低下は興味深い結果であり、さらなるメカニズム的な調査が必要である。
制限点には、試験された特定の用量とスケジュールが、ダルベポエチンの完全な神経保護の窓やメカニズムを反映していない可能性があること、広く使用されるベイリー-IIIが微細なまたは長期的な神経発達の利益を捉えていない可能性があること、高度な支援療法と厳格な輸血プロトコルへのアクセスがある類似のNICU集団に限定されることなどがある。
結論
極端な早産児に対して週1回10 μg/kgで投与されるダルベポエチンは、赤血球量を増加させ、輸血とドナーへの曝露を減少させ、主要な有害事象を増加させることなく効果的である。しかし、この投与スケジュールは、補正年齢22-26ヶ月での神経認知機能の改善には寄与しない。これらの結果は、ダルベポエチンがNICUでの輸血関連の利点を提供する可能性があるものの、神経保護のために単独で推奨することはできないことを示唆している。今後の研究では、異なる用量、タイミング、または他の神経保護戦略との組み合わせを検討する必要がある。
参考文献
1. Ohls RK, Das A, Tan S, Lowe JR, Schibler K, Beauman SS, Bell EF, et al.; Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network. Darbepoetin, Red Cell Mass, and Neuroprotection in Preterm Infants: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2025 Aug 1;179(8):836-845. doi: 10.1001/jamapediatrics.2025.0807. PMID: 40354084; PMCID: PMC12070281.
2. Widness JA, Veng-Pedersen P, Peters C, et al. Erythropoietin pharmacokinetics in preterm infants: Implications for clinical use. J Pediatr. 1996;128(4):522-527.
3. Juul SE, Comstock BA, Heagerty PJ, et al. High-dose erythropoietin for asphyxia and encephalopathy (HEAL): a randomized clinical trial. JAMA. 2020;324(6):529-538.