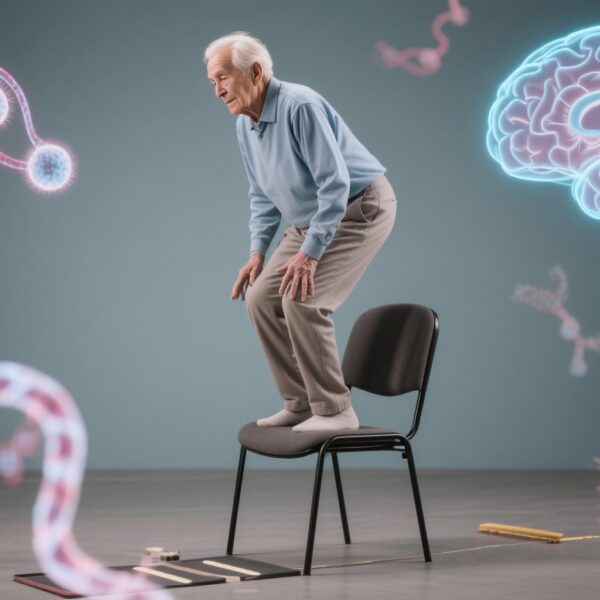ハイライト
- 本研究では、複合的な介入(認知訓練、心身運動、看護師主導のリスク因子修正)を単独の看護師主導のリスク因子修正と一般的な健康アドバイスと比較するために、軽度認知障害(MCI)を有する高齢者を対象とした。
- 15ヶ月またはそれ以前のフォローアップでADAS-Cogによる認知機能評価では、3群間で統計的に有意な差は見られなかった。
- これらの介入を一次保健医療に取り入れるには、さらなる改良と証拠が必要であることが示唆された。
研究背景
軽度認知障害(MCI)は、正常老化と認知症の中間の認知状態であり、日常機能に大きな影響を与えない程度の測定可能な認知機能低下を特徴とする。世界中で高齢化が進むにつれて、MCIの有病率は上昇しており、これらの個体は認知症への進行リスクが高まっているため、臨床的な課題となっている。現在、MCIの進行を止めるか逆転させる確定的な薬物治療法はなく、認知訓練や身体運動などの非薬物療法が認知機能低下を遅らせるために提案されている。
看護師主導のリスク因子修正(RFM)プログラムは、血管性および生活習慣に関連するリスクを対象としており、認知機能の悪化を緩和する可能性がある。しかし、看護師主導のRFM介入の効果、特に単独でまたは認知訓練や太極拳などの心身運動と組み合わせた場合の効果は、実際の一次保健医療環境において不確かなままである。この文脈から、香港で行われた現在の無作為化比較試験(RCT)は、心身運動、認知訓練、看護師主導のRFM(CPR)が、単独の看護師主導のRFMまたは一般的な健康アドバイスと比較して、より優れた認知的利益をもたらすかどうかを評価することを目指している。
研究デザイン
このオープンラベル、盲検エンドポイントのRCTは、15ヶ月間、香港の大学付属の研究・教育クリニックであるLek Yuen Health Centreで実施された。対象者は、60〜80歳の軽度認知障害(香港モントリオール認知評価(HK-MoCA)スコア19〜25点)、安定した身体的健康状態にある地域在住の高齢者であった。
合計456人の参加者が1:1:1で3つのグループに無作為に割り付けられた:
- CPRグループ:認知訓練、週3回3ヶ月間の太極拳運動、四半期ごとの看護師主導のRFM、年2回のプライマリケア医師訪問を受けた。
- RFMグループ:四半期ごとの看護師主導のリスク因子修正、年2回のプライマリケア医師訪問を受けた。
- 健康アドバイスグループ:一般的な健康アドバイスのみのパンフレットを受け取った。
評価時点は、基線、6ヶ月、12ヶ月、15ヶ月であった。主要なアウトカムは、15ヶ月時のアルツハイマー病評価尺度-認知部分(ADAS-Cog)Zスコアによる認知機能であった。二次評価は6ヶ月と12ヶ月での変化を検討した。研究では、少なくとも1回のフォローアップ評価を完了した被験者を含む修正されたITT分析が使用され、ボンフェローニ補正で多重比較を調整した線形混合効果モデルが適用された。評価者とデータ解析者はグループ割り付けに盲検化されていた。
主要な知見
2019年10月から2022年12月の間に、456人が無作為化された:CPR 152人、RFM 152人、健康アドバイス 152人。解析コホートは、少なくとも1回のフォローアップを完了した423人(CPR 139人、RFM 144人、健康アドバイス 140人)で構成された。参加者の平均年齢は70.1歳で、女性が多数(72%)を占めていた。
主要分析では、15ヶ月時のADAS-Cog Zスコアに3群間で統計的に有意な差は見られなかった:
- CPR vs 健康アドバイス: β= -0.04 (95% CI -0.34 to 0.26)
- RFM vs 健康アドバイス: β= -0.14 (95% CI -0.44 to 0.15)
- CPR vs RFM: β= 0.10 (95% CI -0.19 to 0.40)
同様に、6ヶ月または12ヶ月の評価でも有意な認知的利益は見られなかった。これらの結果は、認知機能を改善する上で、看護師主導のRFMに認知訓練と太極拳の心身運動を追加するよりも、標準的な健康アドバイスの方が15ヶ月間で優れていることを示していない。
本研究では、介入に関連する重大な副作用は報告されておらず、これらのアプローチの安全性が確認された。ただし、明確な認知的利益が示されなかったことから、多成分プログラムのリソース配分や患者の負担に関する懸念が提起されている。
専門家コメント
この大規模なRCTは、一次保健医療におけるMCI管理における重要な臨床的問題を扱っており、心身運動、認知訓練、看護師主導のリスク因子修正を組み合わせた多学科的介入は、認知機能低下に関与する複数の機序(血管健康、神経可塑性、身体的適応性)を対象としている。
しかし、統計的または臨床的に意味のある認知機能の改善が見られなかった理由はいくつか考えられる。強度の高い太極拳と認知訓練の期間が3ヶ月では、持続的な神経認知変化を引き起こすのに十分でなかった可能性がある。順守率のばらつきやオープンラベル設計(ただし、アウトカム評価は盲検化されていた)も結果に影響を与える可能性がある。さらに、MCIは異質な状態であり、軌道が異なるため、広範な一次保健医療人口では介入効果が希薄化される可能性がある。
現在の臨床ガイドラインでは、個別化されたリスク因子管理と身体的・認知的活動の促進を推奨しているが、MCIに対する具体的な構造化された多成分介入の証拠は不十分である。今後の研究では、より長いまたはより強度の高い介入プロトコル、リスクプロファイルやバイオマーカーによる患者の層別化、薬物療法との相乗効果の調査を検討するべきである。
結論
本試験の結果、心身運動、認知訓練、看護師主導のリスク因子修正を組み合わせた介入は、一次保健医療設定における軽度認知障害を有する高齢者において、単独の看護師主導のリスク因子修正または健康アドバイスと比較して、認知機能を有意に向上させなかった。これらの知見は、多成分非薬物療法の介入を広く推奨または実装する前に、さらなる改良と堅固な評価が必要であることを強調している。高齢化する人口における認知機能低下を軽減するための効果的、実現可能、スケーラブルな戦略の開発に継続的な努力が必要である。
資金提供と臨床試験登録
本研究は、健康医療研究基金により資金提供された。中国臨床試験登録センターに事前登録され、識別子はChiCTR 1900026857である。
参考文献
Xu Z, Zhang D, Yip BH, Lee EK, Poon PK, Peters R, Yang Z, Lee AT, Leung MK, Wong EL, Mok VC, Lam LC, Wong SY. 軽度認知障害を有する高齢者における一次保健医療における心身運動、認知訓練、看護師主導のリスク因子修正の組み合わせによる認知機能の向上:3群無作為化比較試験. Lancet Healthy Longev. 2025 Apr;6(4):100706. doi:10.1016/j.lanhl.2025.100706. PMID: 40294622.