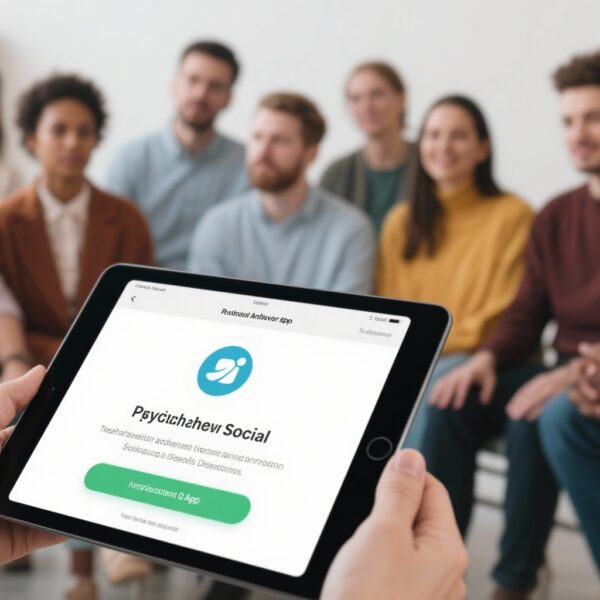ハイライト
- 没入型と非没入型仮想現実(VR)とミラーセラピー(MT)の併用は、ストローク後の上肢機能と手の器用さを改善します。
- 7つのランダム化比較試験(RCT)(475人の患者)のメタアナリシスでは、Fugl-Meyer Assessment-Upper Extremity(FMA-UE)、手機能テスト、Box and Block Testで統計的に有意な効果が示されました。
- FMA-UEの改善は、最小臨床重要差(MCID)の閾値に一貫して達しておらず、統計的有意性があるにもかかわらず、臨床的な影響は限定的です。
- 初期の証拠では、下肢機能、動的バランス、生活の質に潜在的な利点がある可能性が示唆されていますが、さらなる研究が必要です。
背景
ストロークは世界中で長期的な障害の主な原因であり、特に上肢の運動機能障害やバランス障害、生活の質の低下を引き起こすことがあります。効果的なリハビリテーション戦略は、機能的結果と自立性の向上に不可欠です。従来のアプローチは、患者の動機付けやリソースの制約などの課題に直面することがあります。
仮想現実(VR)は、没入型と非没入型の両方を含み、シミュレートされた環境を作り出すことで、患者の参加を促進し、反復的なタスク指向練習を容易にします。ミラーセラピー(MT)は、鏡を使って健側の肢体を患側に反映させることで視覚フィードバックを提供し、神経可塑性と運動回復の促進に効果があります。最近の革新では、VRとMTを組み合わせることで、没入型の感覚運動フィードバックと視覚錯覚を利用して、ストロークリハビリテーション効果を相乗的に強化できる可能性が提案されています。
研究デザイン
高ららによるこの総説とメタアナリシスは、没入型と非没入型VRとMTを組み合わせたストロークリハビリテーションの使用を検討したランダム化比較試験を包括的に評価しました。2025年1月までの5つの電子データベースを系統的に検索し、未発表のデータを含むグレイリテラチャーレビューも実施しました。
対象となった研究では、ストローク患者が結合VRとMT介入を受け、従来の治療またはコントロール介入と比較されました。主なアウトカムは、上肢(UE)の運動回復、手の器用さ、機能スケールに焦点を当てました。バイアスのリスクはCochrane Collaborationツールで評価され、証拠の確実性はGRADE手法で等級付けされました。
主要な知見
14のRCT(475人の参加者)が含まれました。そのうち、7つのRCTがアウトカムの均質性に基づいてメタアナリシスの対象となりました。
主要アウトカム:上肢運動機能
メタアナリシスでは、Fugl-Meyer Assessment-Upper Extremity(FMA-UE)で測定される上肢運動機能に統計的に有意な改善が示されました(平均差[MD] 3.50、95%信頼区間[CI] 1.47~5.53、P<0.001)。サブグループ分析では、ストローク発症から6ヶ月以上の患者に有意な利益が見られ、亜急性期と慢性期の両方に適用可能であることを示唆しています。
統計的有意性にもかかわらず、観察されたMDはFMA-UEの確立された最小臨床重要差(MCID)の閾値(約4.25~7.25)を下回っており、変化の臨床的意義についての結論を緩和しています。
二次アウトカム:手の器用さと機能
手機能テストのスコアはMD 2.15(95% CI 1.22~3.09、P<0.001)で改善し、Box and Block Testのパフォーマンスも若干改善しました(MD 1.09、95% CI 0.14~2.05、P=0.03)。これらの結果は、結合VRとMT介入により手の器用さと機能的な手の使用が向上したことを示しています。
その他のアウトカム
含まれる試験の叙述的合成では、下肢機能と動的バランスに対する潜在的な肯定的な効果が示唆されましたが、異質な測定法と不十分なデータのためメタアナリシスは行われませんでした。生活の質の改善もいくつかの研究で報告されていますが、将来の厳密な試験での確認が必要です。
安全性と副作用
結合VRとMT介入に関連する重大な副作用は報告されておらず、ストロークリハビリテーション設定での安全性と実現可能性が強調されています。
専門家のコメント
没入型と非没入型VRとミラーセラピーの統合は、多感覚入力と運動学習の強化を提供することで神経可塑性の原則に準拠した新しい多様なリハビリテーションパラダイムを代表しています。
上肢機能の統計的に有意な改善は、このアプローチへの支持を強めていますが、MCID値に対する変化の不十分な大きさは、臨床的翻訳には慎重なアプローチが必要であることを意味しています。介入プロトコル、使用されるVRシステム、治療量、患者特性の異質性が異なる結果に寄与している可能性があり、標準化が求められています。
さらに、下肢機能とバランスの利点を支持する有望だが初期の証拠は、将来の研究の方向性を示唆しています。標準化されたアウトカム測定と長期的なフォローアップを持つより大規模でよく設計されたRCTが、これらの結果を検証し、長期的な持続性を評価するために必要です。
結論
没入型と非没入型VRとミラーセラピーの併用は、ストローク患者の上肢運動機能と手の器用さを改善する有望な非薬物介入です。中程度の質の証拠と統計的な改善が支持されていますが、現在のMCID基準に基づく臨床的意義は限定的です。
将来の研究では、介入プロトコルの最適化、下肢とバランスのアウトカムの調査範囲の拡大、生活の質など患者中心の指標の探索に重点を置くべきです。この革新的なリハビリテーションアプローチは、参加型、多感覚、技術駆動型の療法を通じて最大限の回復を目指す現代の神経リハビリテーション戦略に準拠しています。
資金源と登録
この総説の特定の資金源は、元の出版物で報告されていません。記事には、臨床試験の登録情報が提供されていません。
参考文献
高 C, 陳 Y, 魏 Y, 邱 Y, 宋 H, 轨 C, 高 Q. ストローク患者に対する没入型と非没入型仮想現実とミラーセラピーの併用: ランダム化比較試験の総説とメタアナリシス. J Med Internet Res. 2025年10月10日;27:e73142. doi: 10.2196/73142. PMID: 41071983; PMCID: PMC12513685.
ストロークリハビリテーションにおけるVRとMTに関する追加の支持文献:
– Laver KE, George S, Thomas S, Deutsch JE, Crotty M. ストロークリハビリテーションのための仮想現実. Cochrane Database Syst Rev. 2017年11月20日;11(11):CD008349.
– Thieme H, Mehrholz J, Pohl M, Behrens J, Dohle C. ストローク後の運動機能改善のためのミラーセラピー. Cochrane Database Syst Rev. 2018年7月24日;7(7):CD008449.