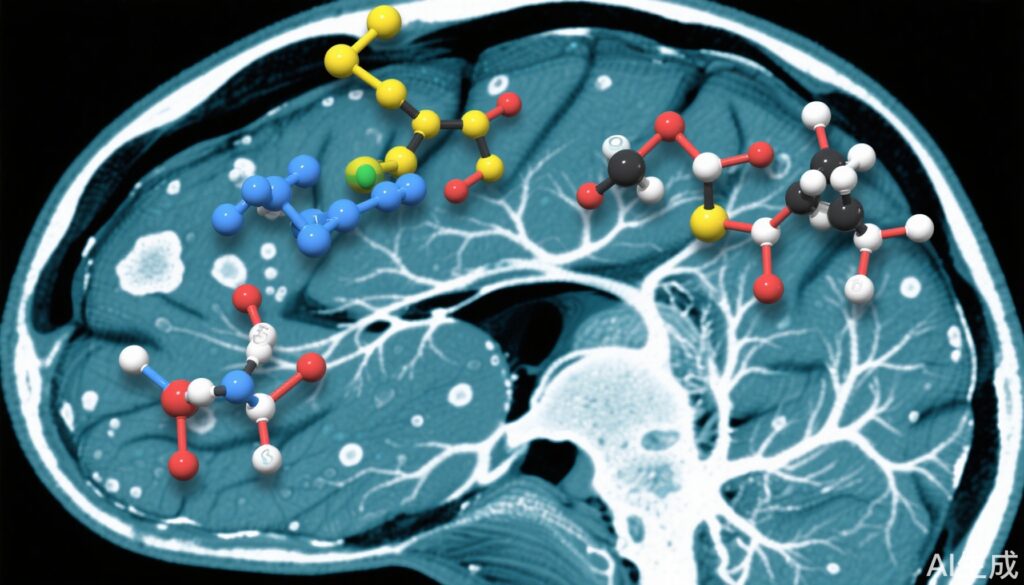ハイライト
- トレビルチニブは、プラセボと比較して、再発のない二次進行型多発性硬化症(SPMS)において持続的な障害進行リスクを低下させました。
- 再発型多発性硬化症(RMS)では、トレビルチニブはテリフラノミドに比べて年間再発率の低下で優れていないことが示されました。
- トレビルチニブの安全性に関する兆候には、重大な有害事象の頻度増加、肝酵素上昇、および軽微な出血の増加が含まれます。
臨床背景と疾患負担
多発性硬化症は、中枢神経系の慢性免疫介在性疾患であり、脱髄と神経変性を特徴としています。多発性硬化症の臨床経過は異質で、再発寛解型(RMS)や進行型(例:二次進行型多発性硬化症(SPMS))などがあります。特に再発のないSPMSにおける障害蓄積は、現在の病態修飾療法(DMT)が再発とは無関係に進行を遅らせる効果が限られているため、重要な未充足の需要となっています。持続的な神経炎症、特にミクログリアとB細胞の関与が、この進行性の悪化に寄与していると考えられています。現在、再発のないSPMSに対する承認済みの治療法はなく、新たな介入の必要性が強調されています。
研究方法
2025年に『ニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』に掲載された2つの主要な第3相試験が、脳内浸透性の経口ブリュトン酪酸キナーゼ(BTK)阻害薬であるトレビルチニブの多発性硬化症への役割について報告しています。
1. HERCULES試験(再発のないSPMS):
– 設計:無作為化、二重盲検、プラセボ対照、イベント駆動型第3相試験。
– 対象者:非再発SPMS患者1131人(トレビルチニブ群754人、プラセボ群377人)。
– 干渉:トレビルチニブ60 mg/日1回またはプラセボ。
– 主要評価項目:少なくとも6ヶ月持続する確認された障害進行。
2. GEMINI 1 & 2試験(再発型MS):
– 設計:2つの無作為化、二重盲検、ダブルダミー、イベント駆動型第3相試験。
– 対象者:GEMINI 1は974人、GEMINI 2は899人の再発型MS患者。
– 干渉:トレビルチニブ60 mg/日1回またはテリフラノミド14 mg/日1回、それぞれに一致するプラセボ。
– 主要評価項目:年間再発率。主要二次評価項目:少なくとも6ヶ月持続する確認された障害悪化。
主要な知見
HERCULES(再発のないSPMS):
– 中央値フォローアップ期間:133週。
– 少なくとも6ヶ月持続する確認された障害進行は、トレビルチニブ群で22.6%、プラセボ群で30.7%(ハザード比0.69;95%信頼区間0.55-0.88;P=0.003)で、進行リスクの有意な低下が示されました。
– 重大な有害事象は、トレビルチニブ群(15.0%)でプラセボ群(10.4%)よりも高かった。
– アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)が正常上限の3倍以上上昇したのは、トレビルチニブ群で4.0%、プラセボ群で1.6%でした。
GEMINI 1 & 2(再発型MS):
– 中央値フォローアップ期間:139週。
– 年間再発率:GEMINI 1 – トレビルチニブ群0.13、テリフラノミド群0.12(率比1.06;95%信頼区間0.81-1.39;P=0.67)。GEMINI 2 – 両群とも0.11(率比1.00;95%信頼区間0.75-1.32;P=0.98)。
– 少なくとも6ヶ月持続する確認された障害悪化:プールデータではトレビルチニブ群8.3%、テリフラノミド群11.3%(ハザード比0.71;95%信頼区間0.53-0.95)。ただし、この評価項目に対する正式な仮説検定は行われていません。
– 不良事象の頻度は両群で類似していましたが、トレビルチニブ群では点状出血と月経量增多がより一般的でした(点状出血:4.5% vs. 0.3%;月経量增多:2.6% vs. 1.0%)。
メカニズムの洞察と生物学的妥当性
トレビルチニブはBTK阻害薬であり、末梢および中枢神経系内のB細胞と単球細胞(ミクログリアを含む)を標的とします。これらの免疫コンパートメントの調整により、進行性多発性硬化症の原因となる持続的な神経炎症を抑制することが推測されます。再発のないSPMSにおける持続的な障害進行の減少は、既存のDMTによって対処されていない神経変性パスウェイに影響を与える可能性があることを示唆しています。
専門家のコメント
HERCULESの結果は、再発のないSPMSに対する効果的な選択肢が歴史的に不足していたことを考えると、臨床的に意味があります。一方、GEMINIの結果は、トレビルチニブが既存の経口DMTであるテリフラノミドよりもRMSの再発制御で優れていないことを示しており、BTK阻害が再発抑制よりも神経変性進行に対してより関連している可能性を示唆しています。肝酵素上昇や軽微な出血イベントの頻度増加は、慎重な安全性監視を必要とします。
論争点と制限
– 再発型MSにおけるトレビルチニブの持続的な障害進行に対する効果は、階層的検定制約のためGEMINI試験で正式にテストされませんでした。
– SPMSにおける持続的な障害進行の減少は統計的に有意ですが、有害事象の頻度増加、特に肝毒性とのバランスを取る必要があります。
– テリフラノミドと比較して再発率の低下が見られなかったため、RMSにおけるトレビルチニブへの熱意は限定的かもしれません。少なくとも、試験用量と対象群においてはそうです。
– 様々なMS集団や長期使用への一般化可能性はまだ確立されていません。
結論
トレビルチニブは、再発のないSPMSにおける持続的な障害進行の有意な減少を示し、緊急の治療ギャップに対応しています。しかし、再発型MSにおける再発予防効果はテリフラノミドに及ばず、安全性プロファイルは特に肝毒性と出血に対する注意が必要です。BTK阻害は、進行性MSの表現型に対して有望な道筋であるものの、最適な臨床的な役割を明確にするためにはさらなる研究が必要です。
参考文献
Fox RJ, Bar-Or A, Traboulsee A, Oreja-Guevara C, Giovannoni G, Vermersch P, Syed S, Li Y, Vargas WS, Turner TJ, Wallstroem E, Reich DS; HERCULES Trial Group. Tolebrutinib in Nonrelapsing Secondary Progressive Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2025 May 15;392(19):1883-1892. doi: 10.1056/NEJMoa2415988 IF: 78.5 Q1 . Epub 2025 Apr 8. PMID: 40202696 IF: 78.5 Q1 .
Oh J, Arnold DL, Cree BAC, Ionete C, Kim HJ, Sormani MP, Syed S, Chen Y, Maxwell CR, Benoit P, Turner TJ, Wallstroem E, Wiendl H; Tolebrutinib Phase 3 GEMINI 1 and 2 Trial Group. Tolebrutinib versus Teriflunomide in Relapsing Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2025 May 15;392(19):1893-1904. doi: 10.1056/NEJMoa2415985 IF: 78.5 Q1 . Epub 2025 Apr 8. PMID: 40202623 IF: 78.5 Q1 .